- ホーム
- > 電子書籍
- > ビジネス・経営・経済
内容説明
■経済学の理論と第一次史料の分析をもとに、日本の経済発展の論理を一貫して研究、経済史研究のフロンティアを切り開いてきた著者による「歴史からみた日本経済論」。
■メッセージは明快、刺激的で、歴史をベースに現在、未来を見通す格好の視点を提供する:
マクロ政策については、アベノミクスの柱の一つ、「高橋財政」をモデルとするリフレ政策、異次元緩和の誤りを指摘。異次元緩和に固執するのではなく、経済成長の趨勢を引き上げるための施策に政策の重点を移すべきだ、将来のインフレリスクに備えることこそ肝心だ、と主張します。
■戦前戦後を通じての日本経済の成長の源泉は1980年代には枯渇していた。それが今日の長期停滞の背景だ、と喝破。成長率を再び高めるには、イノベーションを醸成する政策、新たなビジネスモデル、新規参入の活性化が必要だ。こうした成長政策の舵取りと実行力は、戦前の産業構造の変化や、戦後の「所得倍増計画」に学ぶことができると説きます。人材育成、イノベーション醸成の点で、現在の高等教育の貧困、大学の置かれた惨状についてもきびしく批判します。
■東芝問題に象徴される企業ガバナンスについても、戦前の社外取締役の努力と奮闘、財閥の機能に学ぶことが多いと説きます。また、憲法改正の動きに関連して取り上げる戦前の秘密保護法、国家総動員法の帰結についての記述も、論争的であり、刺激的な内容になっていいます。
■全編にわたり、日本経済めぐるエピソードを通じて、現在の政策や制度、組織のあり方などについての豊富な示唆が繰り出されます。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
KAZOO
masabi
ペンギン伊予守
A.Sakurai
templecity
-

- 電子書籍
- 吸血鬼ドラキュラ
-

- 電子書籍
- 少女M【分冊版】16
-

- 電子書籍
- JWings(ジェイウイング)2024…
-
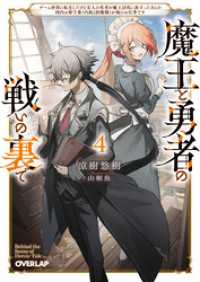
- 電子書籍
- 魔王と勇者の戦いの裏で 4 ~ゲーム世…
-
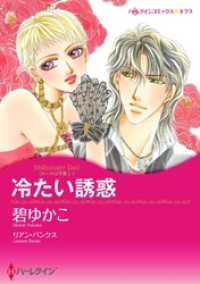
- 電子書籍
- 冷たい誘惑〈ルールは不要 I〉【分冊】…




