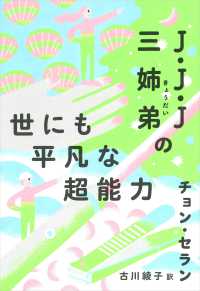内容説明
京都の歴史は、千二百年を超える都市のなかで育まれた、神々への信仰と祭礼文化の歴史でもある。本書は、市内約三百の神社から、京都を代表する下鴨・上賀茂神社、松尾大社、伏見稲荷大社、八坂神社、北野天満宮、上・下御霊神社、今宮神社、平安神宮とその祭礼などを紹介。祭神はどのような性格をもち、なぜ祀られたのか。どのような氏子たちが支えてきたか。祭礼に込められた意味とは何か。秘められた歴史と特徴を解読する。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
HANA
54
葵、祇園、松尾。京都における祭りの位相や歴史を論じた一冊。重点を置かれているのはやはり祇園祭や葵祭だが、その他の様々な祭りも懇切丁寧に解説されており実に興味深い。面白く感じたのが祭りを地域別だけではなく、平安以前から安土桃山に至るまで通史的に論じた部分。こうすることで祭りの違いや内容の変遷といったものが、一層よく理解できるようになっているように思う。祭りの都市的性格や氏子の線引きの問題、山鉾と剣鉾や内容の伝播等も初めて教えられる部分ばかりで面白い。読みながらあの独特の祇園囃子が脳裏に甦ってきそうだった。2015/12/02
ともとも
31
京都、多くの寺社があって、歴史や文化や伝統もある。 京都で執り行われる祭りにはこんな由来があって、それを人と時間が紡いでいき 後世へと繋いでいく。 いろいろと学ばされること、考えさせられることもありながらも、 またさらに京都という地への愛が深まったかのような感じでもありますし、 こうした祭りは、大切にしていかなければいけないと しみじみ思わされてしまいました。 そして、祭りの時に訪れてみたくもなってしまいました。 2015/12/19
エドワード
24
子供の頃から京都の神社の祭に接していると、氏神様・お旅所などの言葉が日常となり、改めて意味を考えたことが無い。我が家は今宮神社の氏子。なるほど氏子の地域はこの範囲か、祇園祭の出し物はなぜ「山鉾」というのか、蘇民将来子孫也とはどういう意味か、本来の意味や起源を再認識できる良い本だった。地味な神事より派手な出し物に興味が集まるのは平安時代も同じ。現代では祭は地元住民が担っているが、神事として始まった祭が変容していく過程が説得力をもって解明されていく。だけどまだまだわからない不思議な祭祀があるのが京都である。2019/11/18
クラムボン
20
京都の代表的な九つの神社について、昔から在る4社(上鴨・下賀茂・松尾・伏見稲荷)と、平安京後の5社(八坂・北野・上御霊・下御霊・今宮)に分けて説明してくれたお蔭で、神社の性格の違いなどが、歴史の流れの中でスッキリ!わかり易かった。全ての神社が平安京の区域の外側に在ることが肝要。祭りの時には氏子の区域に神輿で迎え入れ、神に芸能を堪能して頂き、神社にお帰り頂く。この様なシステムがどうやら《祭り》らしい。私にとっては、少しディープな京都が垣間見れました。2022/02/03
浅香山三郎
17
観光の目的にもなつてゐる京都の祭りをより深く、基本的な事項から掘り下げる。さうすると、賀茂社の祭礼の古くからの形態や、都市民にとつての祭りの意味など、ふだん見てゐる祭りの背景がよく理解される。中公新書らしい手堅い好著。2019/06/02
-

- 和書
- 音楽ノート「12段」