- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
日本のみならず、世界中の人をひきつける有数の観光地、京都。なぜ、京都は今の京都になってきたのか、その過程を探る。対象となるのは名高い京都の神社仏閣だ。それぞれに歴史があり、謎がある。その謎を一つ一つ解いていくと、今とは違う姿をとっていたことが明らかになってくる。「清水の舞台は飛び降りるためにあった?」「焼失前の金閣寺の姿とは?」「苔寺に苔はあったのか?」京都のいまだ隠された魅力を見つけ、人を惹きつけてやまない源泉を明らかにする。
目次
第一章 稲荷山に千本鳥居はいつ出現したのか/第二章 八坂神社に祀られた祟る神の威力/第三章 清水の舞台は飛び降りるためにある/第四章 苔寺に苔は生えていなかった?!/第五章 どんな金閣寺が焼けたのか/第六章 金閣寺の正体/第七章 銀はなくても銀閣寺/第八章 密教空間としての平等院鳳凰堂/第九章 京都の鬼門と裏鬼門
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
そうたそ
19
★★★★☆ 京都の様々な名所の魅力を考察する一冊。著者の専門である宗教学の観点からはもちろん、様々な観点から論じられており非常に面白かった。安っぽい新書のようなタイトルが、本書の内容を端的に表しているとは言いがたく、そこが残念な部分ではあるが、人気の観光地としての京都があるのは現代だからこそという著者の考えには頷ける部分がある。確かに季節の折々で様々な色を見せてくれる京都ほどインスタ映えと言える観光地は他にないだろう。2020/02/07
ふるい
15
なかなか面白く読みました。金閣寺は焼失前の姿をそのまま再建した訳ではなく、意図的?にキンキラキンにしたとか、鮮烈な赤が印象的な千本鳥居は実は近年になって出来たものだとか、京都の代表的な神社仏閣の由来がコンパクトにまとまって書かれています。特に多くのページが割かれている金閣寺が、現在ここまでの人気になったのはやはり三島由紀夫のあの小説があったことが欠かせない要素なのですね。金閣銀閣はおろか清水寺すら生で見たことのない私ですが、俄然京都に行きたくなりました。2018/06/27
yyrn
13
京都ヨイショ本のような書名ながら、そんなことはなく、宗教学者が書いた真面目な本で、ブラタモリ的な大衆受けするご当地案内の対極にあるような、硬派な京都案内本だった。しかし、新書版なのでそれほど重くもなく、誰でも知っている清水寺や金閣寺・銀閣寺、平等院鳳凰堂や千本鳥居の伏見稲荷神社などの、しかし、あまり表には出てこない歴史を教えられて、また京都に行きたくなった。昔を知らなくても十分楽しめる街だが、昔を知ったうえで訪ねれば感激度合いはさらに高まり、思わず隣を歩く訪日外国人に教えてあげたくなりそうだ(笑)。2018/07/19
noko
12
京都に行きたくて研究中。京都には凄い数の寺や神社があるが、深く歴史を知らない。伏見稲荷の千本鳥居、有名だし人気だが、明治に入ってから建てられるようになった。歴史的には最近なんだな。八阪神社の祭神は神仏分離で変更された。前は牛頭天王でよく正体がわかっていない。病や災厄をもたらすともされる。清水寺の舞台から飛び降りる人が昔はかなりいた。生存率は85%だが、歳を取るほど亡くなる。今は下が当時と違うからダメ。京都旅ブームは、新幹線や高層道路の発達と、写真がカラー化されたから。白黒ではなくカラーで見る京都は美しい。2021/06/25
gtn
12
京都が一番である根拠に、著者は神社仏閣を挙げる。特に、金閣寺の焼失は不幸だったが、そのおかげで三島由紀夫がその美を見いだし、再建後にも関わらず人を引き付ける存在になったとの考察がいい。神社仏閣をはじめとする京都ブランドを求め、夏は焦熱地獄、冬は極寒地獄の京都に外国人観光客があふれる。再び訪れてくれるかなと少し心配になる。2018/12/01
-

- 電子書籍
- 主人公と悪役の育成をしくじりました【タ…
-

- 電子書籍
- 【単話版】隻眼・隻腕・隻脚の魔術師@C…
-

- 電子書籍
- 顔に出ない柏田さんと顔に出る太田君【分…
-

- 電子書籍
- 転生しました、サラナ・キンジェです。ご…
-
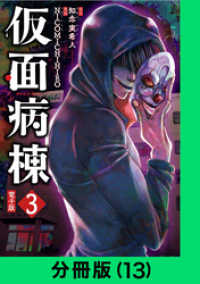
- 電子書籍
- 仮面病棟【分冊版(13)】 LINEコ…




