内容説明
●「仮想通貨」「現金消滅」「銀行消滅」の時代!
いつの世も「お金」で狂乱する日本人――
だからこそ「お金」で振り返る歴史の教養!
人やモノではなく「お金の動き」で見ると
日本史の根幹がわかり、歴史は100倍面白くなる!
原始の物々交換から、貨幣の誕生・流通、
現代の仮想通貨、貨幣消滅・銀行消滅の近未来まで、
私たち日本人と「お金」の深いかかわりを読み解く
ビジネスにも役立つ新たな視点の日本史の必読書。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
kawa
32
古代から現代までお金を切り口に日本史の蘊蓄を語る。テーマが絞られているだけに、話題が細切れで歴史のうねりが感じられないのは仕方がないところか。明治の世で貧しい農村から海外に出稼ぎの「からゆきさん」、その数の多さと国内への仕送りが外貨獲得に貢献は、歴史の陰に隠された切ない事実。国内の貧困の解決策としての海外移住。米国・ハワイに始まり南米、そして各地の排外運動から満州を経て悲劇の敗戦につながる。経済と戦争は切っても切れない関係。2025/10/17
hk
18
■備忘雑記■ 『寺社の庶民化は室町時代~一揆の下地が誕生~』 寺社のパトロンは次のように変遷した。奈良時代は皇室、平安時代は貴族、鎌倉時代は武家。だが鎌倉後期になると武士の寺社離れが進み資金不足に陥った。そこで寺社はそれまで見向きもしなかった農民たちに秋波を送る。賽銭箱を設置して「チリも積もれば山となる」のメンタリティーで財源を確保したのだ。こうして寺社と農民の結びつきが室町時代になってようやく生まれる。これは室町以降に寺社勢力と百姓が一衣帯水となって一揆が起こる苗床となった。……阿弥陀も銭で光るですな…2018/06/27
4fdo4
15
古墳時代の物々交換から現代のキャッシュレスまで、ざーっと日本史に関わるお金の話。 興味があったのが、長らく皇族以外の参拝を拒んでいた伊勢神宮が、一般庶民にも参詣させ 賽銭を納めさせるようになったという歴史。その背景は室町時代以降の皇族貴族の著しい財力低下。 それにより、寺社は大スポンサーに頼れなくなったと。なるほどね。それでお伊勢さんも自力で収入を得る道へ進んだと。そうなれば賽銭だけでなく、飲食や土産屋といった門前町も栄える。なるほどね。 2021/02/27
フク
5
戦国時代の群雄割拠のブロック経済という表現に腹落ち。 永楽銭が舶来品と知ってちょっと驚いた。2018/06/08
くらーく
2
仁徳天皇陵(今は大仙古墳って言うんだね)は、800億円程度で出来たそうで。今なら20億円だって。単なる土木工事だからだそうで。ピラミッドのように回廊は無いのか?まあ、あっても大差は無いのかな? あと、貨幣の歴史も面白いね。和同開珎から始まって、最後は軍票まで。信用足りえる貨幣を作るのって大変なのね。今の日本では、そんな事は無いよね、良い時代ですわ。 そう言えば、そろそろ福沢諭吉から渋沢栄一に代るなあ。近所のラーメン屋が券売機を新札対応に出来ないからって、券売機をやめて、現金のみにしていたなあ。面白いね。2024/05/14
-

- 電子書籍
- 男女逆転身代わり王妃【タテヨミ】38 …
-

- 電子書籍
- ヘタレオオカミと毒舌赤ずきん 第30話…
-
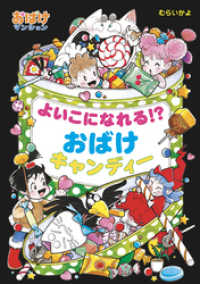
- 電子書籍
- よいこになれる!?おばけキャンディー …
-
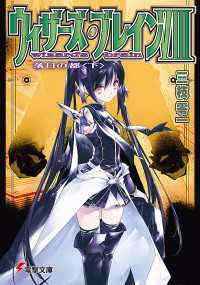
- 電子書籍
- ウィザーズ・ブレインVIII 落日の都…





