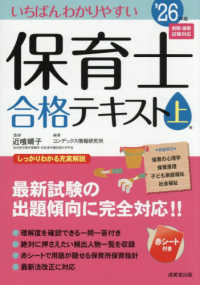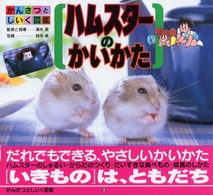内容説明
1923年に建国したトルコ共和国。革命を主導し、建国の父となったムスタファ・ケマルは、共和主義・民族主義・人民主義・国家資本主義・世俗主義・革命主義という6原則を掲げ国家運営の舵を取った。それから約1世紀、数度のクーデタ、オザル首相の政治改革を経たトルコでは、エルドアンが政敵を排除しながら躍進を続けている。ケマルが掲げた6原則を通して、トルコの百年の足跡を振り返る。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
kawa
35
2023年、建国100年を迎えたトルコ共和国の通史(本書は2016年あたりまでのフォロー)。一般教養書、教科書記述のような感じで読みに苦労。今月読了「オスマン帝国 イスラム世界の『柔らかい専制』」「トルコのもう一つの顔」の前に手に取っていたら読了できなかったかも知れないが、これはこれで価値ある一冊。①イスラム教と政治との距離(基本的には政教分離=世俗主義)②クルド・ギリシャ・アルメニア人らの人権問題③キプロスをめぐるギリシャとの軋轢⓸シリア難民問題などをテイクノート。2024/05/23
Isamash
28
1981年生まれ中央大博士の今井宏平・日本貿易振興会機構研究員2017年著作。「オスマン帝国崩壊から」とあるがオスマン帝国には殆ど触れられておらず、最近の政治外交的な史実が中心。知らぬことばかりで、最近の出来事を概略的に知ることができ有難い。NATO加盟国として存在感を感じていたが、その歴史的背景を知ることが出来た。日本と同様に米軍基地を国内に抱えており民族的にはアジアでありながら西洋化を推し進めてきていていて日本との類似性感じた。圧政イメージも膨大なシリア難民を受け入れ、在住クルド人問題の難しさも知る。2022/06/30
かごむし
28
オスマン帝国の栄光と崩壊を引き継いで建国されたトルコ。地政学的にはヨーロッパとアジアの間にあり、ソ連の脅威にさらされ、またイスラム教やクルド人といった宗教・民族問題などの難しい対応に迫られながらも、現実主義的な政策で国家運営を行うトルコ90年に及ぶ政治史、経済史。トルコのことはエルトゥールル号とエルドアン大統領の名前くらいしか知らなかったので、人名、政党、地理などが次々に出てきて読むのに難儀したが、トルコをとても身近に感じられるよい読書となった。公平な記述の中にも著者のトルコ愛がにじみ出てて好感が持てた。2017/10/05
鯖
25
ケマルからエルドアンまでのトルコ現代史。ケマルの提示した六本の矢(共和主義 民族主義 人民主義 国家資本主義 世俗主義 革命主義)から始まり、イスラムの影響が強くなる昨今。60年のクーデターで首相ら3人が死刑になったけど、自殺図ったから意識戻った日にきちんと死刑にしたというのがオイオイオイ…。独裁者だと批判されるエルドアンだけどクルド人が人口の2割越えとなってくると色々大変なんだろうなあとは思う。シリアもだけど、どっかにでっかくて生きやすい無人の大きな島があればいいのになあと無理なことを思う。2023/04/09
崩紫サロメ
23
ちょっと帯が微妙だが、アタテュルクが掲げた国家建設の指針である「六本の矢」と、それぞれの時代にどのように向きあってきたか、という観点からのトルコ現代史を扱った通史。大統領や首相についての制作を中心に論じているが、第三共和政初期を牽引したオザルに関する記述が多め。親米、新自由主義、EC推進、それと親イスラーム、親クルド、オスマン主義、という矛盾した面を持ち、評価の難しい人物であるが、現在の政権を知る上でも欠かせないだろう。2021/01/25
-

- 電子書籍
- 青雲を駆ける 第10話 ヒーローコミッ…