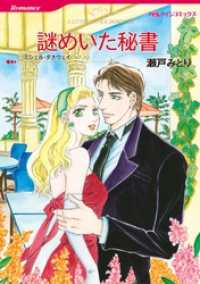内容説明
40年間、太平洋でウナギを追い続けたウナギ博士。その研究の集大成! !
◎天然卵発見秘話
◎稚魚の餌はマリンスノー
◎完全養殖に足りないもの
◎来年以降の資源量変動予測
◎ウナギを絶滅させないために
◎養殖業者に朗報! 幻の絶品「アオウナギ」の作り方
…など、「世界で一番詳しい」ウナギの知識が得られる一冊。
知的興奮を得られる、上質のサイエンスアドベンチャーです。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
キク
29
「天然のウナギの卵は発見されてなくて、産卵場すらわかっていない」ということは知っていた。著者が2009年に、二千年以上誰も見つけられなかったウナギの天然卵をマリアナ海で発見したと知って、読んでみた。ウナギの養殖の完全サイクルはまだ確立されておらず、いわゆる養殖モノは海で捕獲したシラスウナギを大きくしてから出荷している。でも天然卵の発見により、完全養殖サイクルが確立されるかもしれないらしい。マグロの養殖に成功した近大が、次はウナギに取り組むとのこと。ウナギが安くなったら、塚本さんに感謝しながら食べよう。2021/01/10
1.3manen
25
若手研究者、毎日が面白くない人、 ぶらぶらしている人、 興味が持てない人、 真剣になるものがない人にも、 本書を読んでもらいたいと 著者が宣伝される(008頁~)。 天下の東大の先生がおっしゃるなら、 確実な内容だろう。 団塊世代の先生で、 個人的にはあまり好きでない。 自分の専門に関心を引くのはよいが、 万人がウナギに関心をもつ とは限らない。 素人ゆえにつかみどころはないのだ。 生きていれば105歳になっていた 祖母は、木曾川のウナギを食べて 育ったので、歯が丈夫であった。 2014/06/23
ポコロコ
10
「鳥類学者だからって〜」が面白かったので生物学系繋がりで読んでみた。文体は鳥類学者と比べて全然ふざけてないけどこれも面白かった。耳石とか海洋フロントとか初めて知ることが多く新鮮。今週のチコちゃんで解説していた金子豊二先生の名前が出てきて縁を感じた。学校は経済学部入ったけど理系科目がもっとできれば生物系も良かったなぁ2019/05/25
Uzundk
8
古代ギリシャの時代から2400年間謎のままだった鰻の産卵生態について、その手がかりを掴むまでの一連の航海と考察と調査を語る。鰻の原型は深海魚で何らかの理由、ここでは餌の不足のために深海から近海、そしてより栄養のある川へと向かう個体が鰻という種類になったのではないかと考察されている。耳石による齢と水温、水質の解析、獲れないことも含めて調査するグリッドサーベイなどで少しずつ当たりを付けて、産卵場所を大海原の中のある海山周辺にまで絞り込む根気強い挑戦に読んでいる方も興奮を覚えた。2016/09/22
cape
6
ウナギを追いかけた第一人者が、試行錯誤しながら謎であったウナギの生態に迫る話は、ライトなサイエンスノンフィクションながら、研究者には相当へヴィーだろうなという話。かつてミステリアスな存在だったウナギの一生がわかってきて、それはすばらしい成果だが、謎に包まれているが故の魅力がなくなってしまうというのは、なんという皮肉。まだ不明な点も多いそうだが、一般庶民たる自分が興味を持てるレベルの謎はもう少ないかも。すでに人口に膾炙しているためか、おもしろみも半減。とはいえ、ウナギはおいしい。今度はその秘密を知りたい。2015/04/16