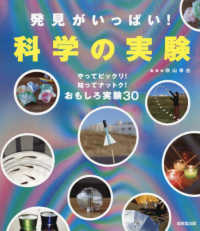内容説明
230年の長きにわたり、信仰を守った潜伏キリシタン。2018年6月には世界遺産登録も予定されている。しかし本当に彼らはキリシタンを唯一の宗教としていたのだろうか。潜伏キリシタンの驚きの姿を明らかにする。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
夜間飛行
195
多神教の風土に生きた日本人にとって基督教は新しい神を付け加えたに過ぎなかった。民衆は、唯一神が世界を創ったことや、人間の罪をイエスが背負われたことを理解できぬまま現世利益を願い、仏像やガラクタを拝んだのだ。言葉の壁は厚かった。通訳がデウスを大日と訳したためザヒエルが山口の広場で毎晩「大日拝みあれ」と叫んだという逸話は、言葉の難しさと大切さを伝える。やがて宣教師がいなくなると、祈る行為はますます教えから離れて呪術化した。潜伏キリシタンは禁教令すら知らず、ただ言い伝えで人に漏らさぬよう受け継いでいったらしい。2024/12/12
それいゆ
49
230年間、一人の指導者もいない中で信仰を保つことなどありえないことです。大浦天主堂に現れた潜伏していた浦上のキリシタン信徒たちが、「サンタマリアの御像はどこ?」と本当に言ったのか?この信徒発見の話は、私は以前から疑問に思っていました。彼らの信仰は、キリスト教とはみなせぬほど異宗化したものであったことは間違いなく、長文の祈りはただ暗記しているだけで、意味は分からない。キリシタンたちは命がけで信仰を守り通したが、その信仰はキリシタンとは呼ぶことのできない別のものであった、という考え、そのとおりだと思います。2018/09/30
かおりんご
31
これを読むと、潜伏キリシタンの方たちが本当にキリストの復活を信じていたのかかなり怪しく感じます。もっとも、今ほど他の国との交流がなかった時代に、どこまでラテン語のミサが理解できていたのか、私も常々疑問ではありましたが。祖先が信じていたものを継承するだけで、命を落としたと思うとかなり切ない。本来のキリスト教とはかなりほど遠い形での信仰だったようですしね。でも、遠藤周作を始め、カトリック司教団も長い間キリスト教が信仰されてきたと書いているのが、この本を読んだあとだとなんとも胡散臭い。2018/05/08
Sato
21
今年長崎県の潜伏キリシタン関連施設が世界遺産に登録された。キリスト教の渡来は戦国時代であり、ラテン語の通訳もいない中、どうやってキリスト教の教義を日本人に伝え理解させたのか?また禁教となり宣教師もいない中、どうやって信仰を守ってきたのか?私はずっと疑問に思っていた。本書はクリスチャンでもある著者が潜伏キリシタンの実態について、あくまでも仮説であるが、潜伏キリシタンが信仰していたものは単なる祖先から伝わる慣習と民族宗教であり真のキリスト教ではないことを日本人の宗教観と共に書かれており興味深い内容であった。2018/08/31
鯖
19
ユネスコが世界遺産に登録勧告とのことで手に取った一冊。この本ではカクレキリシタンは明治の禁教令以後、潜伏キリシタンは江戸期と定義。「隠れ」だと悪いことみたいだから、カタカナにということらしいんだけど「フクシマ」を思い出す流れでどうもなあ…。江戸期に執拗な取締にも屈しなかった理由として、神からのタタリを怖れていたこと、踏み絵は普通に踏んで、そのわらじを鍋で煮て、水を飲めば許されると解釈してたことなどに驚いた。2018/05/06
-
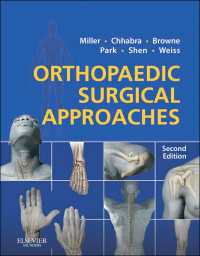
- 洋書電子書籍
-
整形外科アプローチ(第2版)
O…
-

- 電子書籍
- 資源がわかればエネルギー問題が見える …