- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
国力を左右する主な要因は軍事力や工業力、あるいは人口だと考えられることが多い。だが多くの識者にとって盲点となっている重要なファクターが一つある。「物流」である。漢の武帝はヨーロッパに先駆けて、物流に国家が介入するシステムを構築して財政を安定させた。オランダはバルト海地方から輸入した穀物を、食料不足にあえいでいた欧州各地に運搬することで覇権国家となり、イギリスではクロムウェルが航海法を制定したことがパクス・ブリタニカ(イギリスの平和)の要因となった。さらにヴァイキングを駆逐したハンザ商人から、社会主義国家の決定的な弱点まで、経済史研究の俊英が平明に語る。 【内容例】■フェニキア人なくしてローマ帝国はなかった ■イスラーム王朝はいかにして国力を蓄積したのか ■国家なき民は世界史をどう変えたのか――アルメニア人、セファルディム ■アメリカの「海上のフロンティア」とは
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
007 kazu
31
タイトル通りで世界史を物流の視点から西欧、アメリカ、アジアを舞台に概観する。世界の覇権国の移り変わりもこの観点で分析している。フェニキアから社会主義の失敗まで。 視点は新鮮で面白いが新書とは言え、やや広く浅いかなという点も。トリビア的に面白い話は盛沢山だ。この視点で見たとき、現在はどう映るのかの記述があると尚、よかった。 国という観点ではとらえきれないかな?2020/09/30
Miyoshi Hirotaka
31
支那は豊かな国だった。朝貢貿易で欲しいものを持ってきてもらえば足りた。しかし、これは、物流の他国依存。航海術で西洋を凌駕したが、海洋覇権は握ることができなかった理由。オランダはバルト海地方から輸入した穀物を食料不足に喘いでいたヨーロッパ各地に運搬することで覇権国家になった。イギリスはクロムウェルが航海法を制定したことが、パクす・ブリタニカの基礎となり、全世界に物流網を形成、アジア内部の物流まで担った。マルクス経済学は、生産力の増大を重要とし、日常生活用品が流通するシステムは軽視。かくして社会主義は滅んだ。2019/02/18
小木ハム
23
主にヨーロッパとアジアの物流史を広く浅く。お堅い文章なのでページを捲る手が止まらなくなるタイプの本ではないです。また南米やアフリカ、インドネシア等には殆ど触れられていません。物流はフェニキア人の地中海交易が祖というのは初めて知りました。レバノン杉で造船。アルファベットの原型も作ったというのだから大したもんです。『銃、病原菌、鉄』にもありましたが、陸続きの東西の国家間では交易が盛んになるし文明も発達しますね。そのぶん戦争は起きるしコロナ宜しくウィルスも伝播しやすいけど、、2020/03/21
ようはん
21
古代フェニキア人の開拓した地中海の航海ルートがカルタゴに引き継がれてローマの海に繋がった流れ等、世界史を物流という視点から見るテーマの内容は思った以上に新しい知見を得る事が出来た。2022/10/02
inami
17
◉読書 ★3 私たちは、インターネットの発展が、グローバリゼーションの大きな要因であると考えるが、それは間違いなく正しい。同時に、「物流」がどのように発展していったのかという側面に目を向けなければ、グローバリゼーションの重要な一面を見落とすことになってしまう・・と、本書は全17テーマにそって、時代順に述べられている。「1.フェニキア人はなぜ地中海貿易で反映したのか」「4.ヴァイキングはなぜハンザ同盟に敗れたか」「13.イギリスの”茶の文化”はいかにしてつくられたのか」等・・んん〜内容がちょいと想定外でした2018/03/15
-

- 電子書籍
- ひとまず猫と休みます ~OL辞めて猫カ…
-
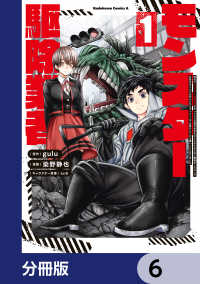
- 電子書籍
- 現代でモンスター駆除業者をやってたら社…
-
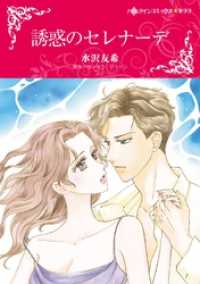
- 電子書籍
- 誘惑のセレナーデ【分冊】 9巻 ハーレ…
-

- 電子書籍
- ル・ボラン2021年1月号
-
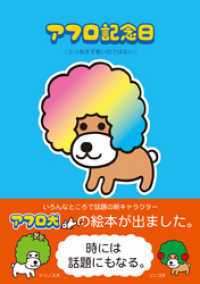
- 電子書籍
- アフロ記念日 ねーねーブックス




