- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
森田正馬、土居健郎、河合隼雄、木村敏、中井久夫。明治以降100年にわたる「心の病」との格闘のなかで、彼らは日本の文化に合った精神医療、心の治療の領域を切り開いてきた。日本人の心とはなにか。その病をどう癒すのか。臨床心理学・精神医学の広範な知見を活かしつつ、独自の人間理解から患者と向き合い続けた五人を取り上げ、その理論の本質と功績をわかりやすく解説する。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
キムチ
48
哲学・心理学の分野における評論家の執筆。50歳代という事で経験知より現代を俯瞰し 語っている。日本の精神医療100年余で大きな足跡を残した5人にスポットライトを当て、理論の本質と功績を簡明に記すと同時に日本人論へ限りなく近づいて行く。現場の変容~DSMⅴ、PSWの誕生、1980以降の精神病理学における人文科学思想的傾向の強まりなども述べられる。森田・土居・河合・木村・中井の業績を具象的に解説してあるので頭の整理になった。「甘え」を含んだ相互依存性の高い2者関係。強い母性原理の精神的存在。道徳意識の底に有る2020/01/05
しょうじ@創作「熾火」執筆中。
27
【1回目】それぞれに単著が必要なほど業績のある5人について俯瞰した「おトク」感にひかれて読み始めた。しかし5月半ばで一旦挫折し、中断を挟んでようやくの読了となった。率直に言って難しかった。どの一人をとっても、少なからぬ縁があるにも関わらずだ。現今のこころの治療とは、脳の器質障害に還元され、あたかも修理するかのように薬物が処方されていると言ってよいだろう。しかし、そこには人間についての深い理解が欠如しているとは言えまいか。この本は深い洞察に満ちた治療論と人間論とを展開している5人を紹介したものである。2018/09/02
かみしの
15
森田正馬、土居健郎、河合隼雄、木村敏、中井久夫という名前は聞いたことがあるけれど、(ぼくにとっては)詳しくをあまり知らない5人の精神科医・心理臨床士の理論と実践を、各々の人間論に焦点を当て紹介している本。西洋の思想をどのように日本ナイズするか、という点においてやはり土居の「甘え」や河合・木村の文化、時間論は面白くて、ぜひとも原著にあたりたくなる。2018/03/27
あっきー
9
✴3 5人はほとんど読んだことがないが、上手くまとめてあり良いとっかかりになった、一番の好みは木村敏だが以前読んで全て忘却してしまった「時間と自己」をいつか再読したい、実は昨年仕事でミスをしてしまい大変な目に遭った、今年も同じ仕事を頼まれたのだが気分的にもう引き受けたくなかったので「うつ病になってしまい、まだ治りきっていない」と断った、たまにはこんなことがあってもいいだろう2018/03/04
ひろか
7
各名人についてわかりやすかった。著者の立ち居位置とも関連するのだろうが、本質は皆共通している。2018/02/09
-
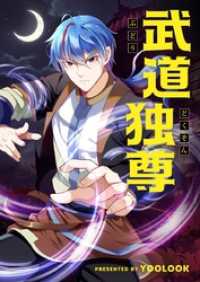
- 電子書籍
- 武道独尊【タテヨミ】第119話 pic…
-

- 電子書籍
- あなたが教えて teaching.8 …
-
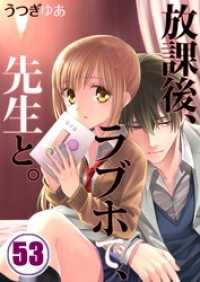
- 電子書籍
- 【フルカラー】放課後、ラブホで、先生と…
-

- 電子書籍
- RIDERS CLUB No.368 …
-

- 電子書籍
- 経済界2014年12月23日号




