内容説明
20世紀を代表する哲学者ジル・ドゥルーズは精神科医フェリックス・ガタリとの協同作業を試み、『アンチ・オイディプス』(1972年)、『千のプラトー』(1980年)、そして『哲学とは何か』(1991年)という三つの著作を残した。これら三冊を貫くただ一つの課題とは何だったのか? 資本主義を打倒し、「革命」を実現するための三つの戦術。精緻な読解を経て、今日の情勢下での有効性を問う、21世紀のスタンダード!
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
;
5
左翼としてドゥルーズ=ガタリを読むための解説書。読みやすかった。2019/06/20
磊落のい
4
読み終えてみて、ヒューマニズムだと思った。言われてるのは、脱領土化、脱領土化、脱領土化。脱領土化とは、欲望が固定的な意味の秩序から解放されること(図解雑学現代思想参照)それをドゥルーズ=ガタリは分裂分析の目的である主体集団の形成に位置付ける。主体集団に対置されるのは、服従集団であり、それは、学校や工場といった資本主義的諸装置によって実現される。そこからの切断的移行、つまりマイノリティ性への生成変化こそが資本主義を打倒する上で重要だと言っている。「状態」からの脱領土化、創造の過程の上に身を置くことの重要性。2017/12/21
2
再読。ただ、アンオプからミルプラを経て「哲学とは」に至って後退戦を強いられている現状がよくわかる。アンオプ=ミルプラが「切断の切断」としての68年的思想であれば「哲学とは」の余りにも資本主義の外部性を喪失した絶望的な(NGO化)された場所はどうか。佐藤、廣瀬共にレーニン的な「切断」つまり「前衛党」による欲望が割って入るための潜在性の現勢化がまず必要であることを認めているのは誠実であると思う。そういう意味では、ドゥルーズ =ガタリをなんとか政治の実践に移行させようとする苛立ちはわかるのだが。2024/02/02
differenciantum
2
野心的かつ精緻な読解で素晴らしい。こういう本が日本から出てきたかと思うと、胸が熱くなる。ラカン、カント、とりわけフーコーとの対峙を通じて形成されたD=Gの実践的な(政治)哲学を説いた本。「権力はなぜ欲望されるのか」「なぜ人間は権力に服従するのか」という問いに徹底的に向き合いながら、(フーコーとはまったく違ったやり方で)そこに新たな未来の人間像を作りだそうとする試み。たとえば岡本祐一朗『フランス現代思想史』(中公新書)の消極的なD=G像を覆そうとするもの。ネグリ=ハートや不可視委員会の著作との併読も奨めたい2018/05/01
トックン
2
3つの革命とは①プロレタリアによる階級闘争(『アン・オイ』)②マイノリティによる公理闘争(『ミル・プラ』)③動物(少数派)を眼前にした人間(多数派)による政治哲学(『哲学とは何か』)を指す。①②と③の間のソ連崩壊を切断線とし楽観から悲観へ至ったとするが、佐藤・廣瀬は前者を重視。結論部で辺野古基地・原発(=ドゥルーズの謂う<問題‐問い>)を沖縄・福島の人に委ねるべきという民族自決主義には疑問。ドゥルーズは<問い>を重視したが、それは「解答」とはセットではなく偶然性(出来事)のシーニュではなかったか。2018/02/25
-
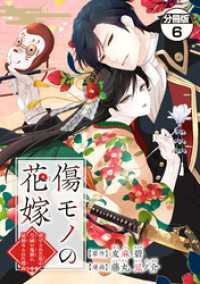
- 電子書籍
- 傷モノの花嫁 分冊版(6) ~虐げられ…
-
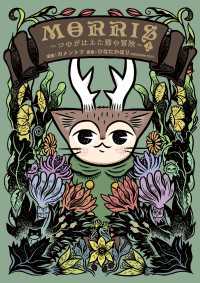
- 電子書籍
- MORRIS ~つのがはえた猫の冒険~…






