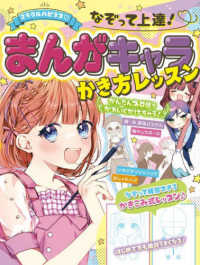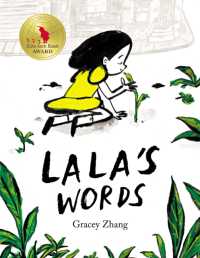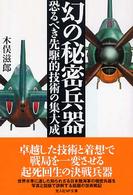- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。
人間にとってカエルとは何か?あるいは、カエルにとって人間とは…?日本でもアジアでも昔から、田園の可愛い生き物として、鳴き声を楽しむ対象として、そして美味しい食材として、カエルは身近な存在でありつづけてきた。そして現代、環境問題を映す鏡にもなっている。カエル釣り歴なんと六〇年!の著者が贈る、可愛くて美味しい両生類をめぐる雑学オンパレード。
目次
第1章 カエルの昔と今
第2章 カエルを釣る
第3章 カエルを食べる
第4章 カエルの民族動物学
第5章 カエルの環境学
第6章 カエルの近縁者たち
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
海星梨
5
蛙繋がりで『青蛙堂鬼談』と一緒に借りました。著者の文章の楽しみかたが分からず、わりと苦痛な読書に。蛙は後ろ足からはえる、サンショウウオは前足からはえるなど面白い話はあったのですが、冗長というか論点が行方不明というか構成力不足というかなんというのやら。2020/02/23
スズツキ
4
学術的なことはほとんどなく、著者の幼少期からのカエルとの関係や世界各国のカエル文化について。疲れた時にもダラダラ読めてよかったです。2015/04/12
こにいせ
3
カエルにまつわる滋味豊かなエッセイ。視点は理系と文系の間くらいだろうか。文章の表現は少々堅いが、そこまで難しいことは書いていないし、文章の意味が非常に取りやすい。中・高校生くらいに是非とも読んで欲しい新書。げこげこ。2010/04/21
うたまる
2
まさか新書で、このタイトルで、内容がカエル雑学エッセイだとは思いもしなかった。まったりとした少年時代の思い出話から始まり、学術的な分類論、カエル釣りや料理の下拵えなどの技術論を経て、カエル文化論へと至る。「ライスカレー黎明時の肉はカエルか鶏」「英語圏でのfrogsとtoadsの違い」「虫の音を楽しむ習慣は中国にもあったが、カエルの鳴き声を楽しむのはさすがに日本だけ」などに感心。普段なら挿入される写真はカラーの方がいいが、今回ばかりは白黒が正解。123頁のウシガエルの皮剥ぎ写真はモノクロでも卒倒ものだった。2017/08/24
抜け忍1号
1
2007年6月10日に読了。この本を読む気になったのは、宮崎哲弥氏の「新書365冊」で本書が高評価を受けていたからだと思う。カエルを釣る遊びや、食材としてのカエル、さらにはカエルが環境問題の象徴となる現代の視点について語られている。昔からカエルが日本やアジアの人々の生活にどのように関わってきたかを知ることができる。特にカエル料理の部分は興味深く、中国の料理文化にも触れている。個人的には、もう少し写真があっても良かったかな?と思った。2007/06/10
-
- 洋書
- Lala's Words