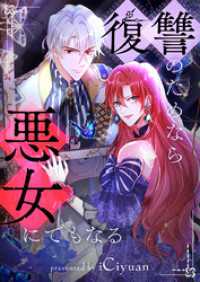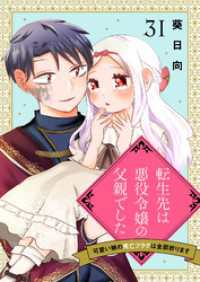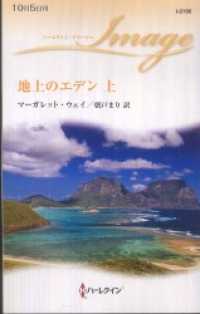- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。
一九世紀、インドの商人達はコミュニティを基盤として、東インド会社や英国資本系巨大企業に囲まれながら、したたかに財閥化していった。だが、英国による植民地政策、独立後の社会主義混合経済のもとで、財閥は翻弄されてゆく。そして、一九九一年の外貨危機を契機とした自由化政策により、新たな成長戦略のなかで再び活力を取り戻した。インド経済の七割を動かす、少数家族の実体とは。
目次
序章 インド財閥とは何か
第1章 財閥の起源と発展
第2章 君臨する最大の財閥、タタ財閥
第3章 復権を狙う、ビルラ財閥
第4章 急成長を続ける、リライアンス財閥
第5章 群雄割拠の中堅財閥
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
mitei
43
ガンジーが暗殺された現場もインドの財閥の敷地内だったことが驚きだった。それだけ地元によっているのかと思ったら、イギリスと仲良くしてたりとあとがきにもあったが若干情けないシーンもあった。しかし日本とはほとんど馴染みのない財閥だから読むもの読むもの新鮮な印象をうけた。2011/11/01
isao_key
8
近年経済成長著しいインド。そのインド経済を支えるインド財閥。本書はインド財閥の起源から新興財閥の現在の姿までをコンパクトにまとめた良書。インド財閥の起源は、二大都市で隆盛した「商人のコミュニティ」にあった。ボンベイを中心に活動したのが「パルシー」「グジャラーティ」で、カルカッタを中心に活動したのが「マルワリ」だという。彼らは「土地」「宗教」「民族」などによって結びつけられた社会的なコミュニティであり古くから商業活動もここを基盤として成り立っていた。またインドのITの強さは、原子力技術開発から始まっている。2013/08/21
Roti
6
インドの大企業のなかの比率、そしてGDPの6~7割は財閥企業によって生み出されているという。そして大きくは「パルシー(ペルシアからの拝火教徒起源)」、「グジャラーティ(グジャラート商人)」「マルワリ(ラジャスタンの商人)」の3つに分かれるという。現在、3大財閥と言われるタタ財閥は「パルシー」、ビルラー財閥は「マルワリ」、リライアンス財閥は「グジャラーティ」である。歴史と商売の変遷、一族経営であるがゆえに内紛からの没落や復興など、読み応えあり。かつインド経済と企業を知るには財閥から理解が必要と知る。2017/10/30
in medio tutissimus ibis.
2
「中産階級は、イギリス人をどけて入れ替わることに依って、この構造を維持し、それを管理していこうとした。これら中産階級はこの構造に挑戦し、これを根絶しようとするにはあまりにも『この構造の産物』であり過ぎたのである」というネルーの言葉が、彼自身を含めたインド、政府、及び財閥に圧し掛かっている。1850年代、セポイの乱がおこり、東インド会社が退場し、イギリスの金融と法がインドの産業革命を起こし、財閥も生まれた。このときの構造が今日まで近代インドを規定しているのではないか。インド自体がひとつの財閥なのではないか。2022/01/23
影実
2
インド経済を動かす財閥およびその成り立ちについて解説した本。植民地時代に始まり、二度の世界大戦、独立運動、独立後の政府の社会主義政策との関係性などがコンパクトにまとまっている。インド三大財閥であるタタ、ビルラ、リライアンスについても重点的に解説しているが、その他中堅財閥の扱いはかなり軽く、純粋に業界地図のようなものを望むと期待はずれかもしれない。読みづらさと2011年時点の情報であるということを除けば、インド財閥についての入門書としては十分な内容だと思う。2017/10/24