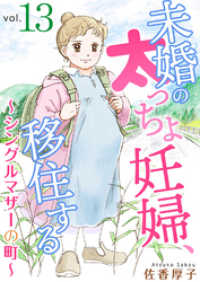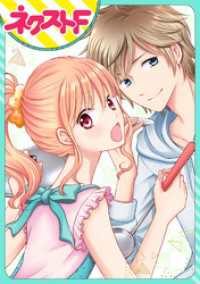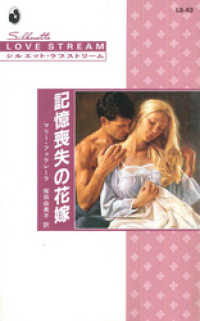- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。
ジャガイモ、トウモロコシ、トウガラシ、トマト、インゲン等々、今や私たちの食卓に欠かせない中南米起源の野菜や穀物を、ルーツの地で人びとはどのように改良し利用してきたのだろうか。海抜五〇〇〇メートルを超えるアンデス高地からバージエと呼ばれる谷間地方、そして低地のアマゾン流域まで、特異な食材と料理、酒を求めて探訪し、知られざる食の文化を初めて紹介する。
目次
第1章 野山のドライブイン
第2章 伝統の味
第3章 高地高原で過ごす
第4章 雨のバージエ
第5章 果実をめぐる
第6章 熱帯アマゾンで
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
キムチ
32
この方は相当な中南米オタク!デスクワークと講義に明け暮れる文化人学者は足元にも及ばない。掲載されている写真が小さく、モノクロなのは安価に、こういった形で情報を提供してくれる方が有難いから当然かも。日本の食生活に深く入り込んでいる源泉をいくつか感じた・・ジャガイモ・トマト・ピーマン・トウモロコシ・コーヒーetc先進国という「高慢な」形容詞と共にどれほどの文化を頂けているか。今尚、自然災害・民族闘争・政情不安・ゲリラ等を背景に「食べられる事が体調を知る目安」で環境と共生する事のみに生きている地域なのだなぁ。2014/05/28
カズザク
2
厳しい自然環境の中で育ったからこそ、『肉』『野菜』『果物』の素材そのものの素朴な美味しさを味わえるアンデス&アマゾン。子どもの頃食べたピーマンってもっと苦かったような?トマトって酸っぱかったような?品種改良が進み、何でも食べやすくなってきている日本‥これでいいんだろうかって疑問?2013/10/14
みい⇔みさまる@この世の悪であれ
2
○…著者はアンデス通、と言うより相当なマニアかもしれません。それぐらいこの本にはアンデスの「食」がぎっしりと詰まっているのですから。高山地域における食のあらゆる物を紹介しており、一手みたいなと思わせてくれる内容でした。新書だからと侮るなかれ。2009/07/09
takao
1
じゃがいも、とうもろこしだけでない。鱒もあれば果物もある。2017/01/23
むとうさん
1
アンデスを旅する写真家が旅先で出会った食生活と人についてまとめた本。単に食材と料理を紹介するだけでなく背後にある文化についても経験をもとに書かれており、読み終わった後に実際にアンデスに行ってきたかのような感覚が残った。美味しそうな料理、食べ物がたくさん出てくるという点ではお腹がすいているときに読むといいかもしれない(笑)。写真家ということで自ら撮影した写真が大量に掲載されているのもポイント。ただし写真が全て白黒なのが若干残念。カラーページが少しでもあるとなおよかった。2011/01/27