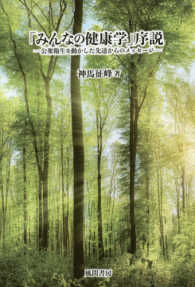内容説明
ノブとハム子は、同じ団地に住む小学六年生。ともに“一人っ子”だが、実はノブには幼いころ交通事故で亡くなった兄がいて、ハム子にも母の再婚で四歳の弟ができた。困った時は助け合う、と密かな同盟を結んだ二人は、年下の転校生、オサムに出会う。お調子者で嘘つきのオサムにもまた、複雑な事情があって――。いまはもう会えない友だちと過ごしたあの頃と、忘れられない奇跡の一瞬を描く物語。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ケイ
143
公子と書いて、ハム子と呼ばれたら…。そう言えば、私の名前の候補を両親があちこちで見てもらって、最終に残った中の1つが『夕子』。それを見た祖母が『タコ』って男の子に虐められるからダメと却下したと聞いていたので、さもありなんと思った。重松清を数冊しか読んでいなかったら感動したと思うが、かなり読み込んでくるとそろそろ切り口を変えて欲しいと思う。それと、女の子でも、まず暴力をふるったら、徹底的に叱らなきゃダメだよ。女の子にそんなこと言ったら…、なんてのは逆差別だと思うよ、大橋君のお母さん。2017/07/04
ぷう蔵
94
小学生の心模様、絶妙に描いているなぁと言う感想である。6年生、4年生なりの微妙な心持ちの違いや、男子と女子の精神的成長の違いまで上手く描写している。「見猿、言わ猿、聞か猿」って、いつの時代からある諺なのか?これって本当にすごい言葉だ。余計な物は見たり言ったり聞いたりしない。いや、目には入るし、話さなければならない場合もある、耳にも入ってくる。だが、あえて見ないふりをしたり、言うことは選んで、聞こえないふりをしてやり過ごすと言う事。それが大人になると言うことか?いや、子どもなりの三猿もあるんだよね…。2017/11/12
扉のこちら側
87
2017年436冊め。やはり公子さんは全国的にハム子とあだ名される宿命なのだろうか(私のことではない念のため)。今作ではハム子がいい感じに小にくたらしいキャラクターで楽しめた。どうしても子ども時代を遠く懐かしむ世代になると美化してしまいがちであるが、あの頃は決して楽しいばかりでも生きやすかったわけでもなかった。会わなくなった彼らはどうしているのだろう。2017/12/24
カブ
79
昭和40年代の小さき者たちのお話。著者と同世代なので学校生活や放課後の様子など懐かしく思う。ただ、同じ子どもだっただけに、他の人の複雑な事情や家庭のことはあったかもしれないけど、たぶん知らなかったのだとわかった。子どもには子どものルールがあって、大人とは別の世界がある。一人っ子同盟の3人のその後が幸せであって欲しい。2017/08/05
ひめありす@灯れ松明の火
72
【新潮部 自由課題】途中でお土産の「見ざる・言わざる・聞かざる」のエピソードが出てくるけれど、彼ら三人は本当にそうだったんだと思う。家族で一人だけお兄ちゃんの影を見ることが出来ないノブ、本当の事は何一つ言うことが出来なかったオサム、周囲の声を聴くことのなかったハム子。それは自己防衛の手段だった。自分の力ではどうしようもない事も、自分で決めたこともどちらもあるけれど。彼らは大人より小さく弱く、まだ何の力も持たない。だけど、彼らを襲ってくる物は大人が思うよりももっと多くて大きくて、時に大人では守り抜けないから2017/08/31
-

- 和書
- 兎に角うさぎがかわいい