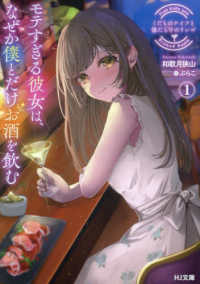内容説明
『笑い』と『不気味なもの』は「反復」といった同じ現象を対象にして出会いかつ分岐する。その二つの論考を並列させると、新たな読み・新たな思考が召喚される。ジリボン「不気味な笑い」を付す。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
くろねこ
7
「不気味なもの」を読む必要がありこちらで再読。以前読んだときは「笑い」の方が初読だったので面白く、フロイトが結局去勢不安に持って行くところに不満足を覚えた。今回はベルクソンとフロイトが異なる方向に行った理由が特に残った。哲学的な思考はどこか距離がある。身をおいて侵蝕されながらそこから考える臨床的なあり方との違いだろうか。ジリボンの最後の言葉「笑いは不安のネガフィルムであると言うことが出来るだろう。だからこそわたしたちは笑いを真剣に受け取る必要がある。」ユーモアに変えることで生き延びる人の強さのことを思う。2020/01/14
かす実
7
ベルクソンによると滑稽なものに対する笑いは、対象が既知の型に当てはまる(=機械的なこわばりがある)とき、それを矯正しようという社会的意図を持って生まれるそうです。つまり、笑いは純粋な行為ではなく、社会の総意による実利的な行為である!また喜劇は他の芸術と違って、限定ではなく普遍を描こうとするという指摘も興味深い。さてこの「笑い」と「不気味なもの」とは、同一あるいは反転の関係にある。前者は枠からの脱出であり後者は枠の破壊・不在。この理論を使って「カメラを止めるな!」を読み解くと、めちゃくちゃ面白いです!2018/08/31
カタクチイワシ
3
ベルクソンが笑いについて分析した「笑い」、フロイトが不気味さについて分析した「不気味なもの」、その両者を踏まえジリボンが笑いと不気味さの違いを分析した「不気味な笑い」の三本が収録されている。哲学的、抽象的な内容に四苦八苦する部分も多かったがなんとか読了。ベルクソンパート、笑いは社会の中でそこからはみ出る行為を矯正する役割だという。同時に、最後に強調される、笑いは「善良であるはずがない」という重要性。またジリボンの「枠」の話はあちこちに適応できると思う。興味深い箇所が非常に多い。また読み返したい。2020/01/11
ねこ
3
これは買い2017/06/28
o
2
壮大な人生の深いところでの探究という哲学の類にはこの本は属さないのだろう これは的確な人間の深いところでの分析であると思われる ここで面白いのがベルクソンの芸術の記述である 114でこの分析の中心的議題となる喜劇を一般的なものを目指す唯一の芸術であり、そこから芸術は分類を脱するものとされる しかしこの唯一だった一般性を目指す芸術は1917年のデュシャンの泉からの現代アートによって拡張されたのではないか 1900年初版のこの本から類型と一般性を介して深みに達するという現代アートの本質が見られるのではないのか2021/08/10