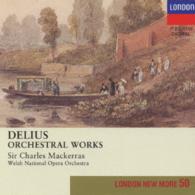内容説明
「統計」と聞けば、自然現象そのもの、或いは機械的な描写のように錯覚される場合が多いが、実は誰かが編集し、分析したもので、その裏には必ず「意図」が存在することを私たちは忘れがちだ。しかしAIの存在意義が高まるこれから、必要なのは本当の意味で正しく統計を使い、読み解く力で、「統計学」こそ世界の共通言語になる、と筆者は主張する。そこで、統計リテラシーを高めることを試みた東大講義、「統計という『言語』の便利な使い方」をベースにした新書をここに。二酸化炭素は温暖化と関係ない? いくらタバコを吸ってもガンにはならない? 統計がヘイトスピーチを加速する? あなたは「統計」に隠された意図を見抜くことができるのか!
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
テイネハイランド
17
図書館本。著書のタイトルが「統計は暴走する」と若干煽情的なのでいやな予感はありましたが、読んでみると、専門家が理路整然と統計について解説するというよりも、自分のいいたいことを客観性をかなぐりすてたかのように周囲にアジる活動家の書く文章のようでしたので、驚きました。著者は東大の教授らしいですが、変わったセンセイもいるものですね。コホート効果、マルコフ性、内生・外生変数など、統計データを理解する上で難しいが重要な用語も本書には出てきますが、別の著者の解説本を読んで、改めて学ぼうと思いました。2017/11/14
Naota_t
6
#2110/★3.3/私は業務の中で、数値を使って説明することもあるため、興味深く読むことができた。統計や表がある場合は、そこに書き手のストーリーやコンテクストがある。人は文章よりも絵や表を先に見るため、騙されないように注意が必要だ。ナチス・ドイツであったように、ステークの不均衡も要注意、常に多数決が正しいわけでもない。「まずは客観的・科学的根拠をいちいち確認する習慣をつける」(p73)「見聞きした膨大な情報をまず常識で言わば一次審査」(p242)するなど、物事を普段から批判的に見ることが重要だ。2024/05/15
まゆまゆ
5
統計とはあくまで誰かが編集して分析したものであり、その裏には必ず意図が存在する。統計リテラシーを身につけ、批判的に読む重要性を説く内容。特にアンケートは制約や背景に思いを馳せることが重要。相関と因果かを見極めることは難しいが大事な視点である。2017/12/04
乱読家 護る会支持!
4
マスコミや左巻き団体からよく使う統計を使った、騙し、盗み、迫害などについて学ぶ。 【統計は騙す】統計資料と本文が論理的につながっていない。相関関係があるから、因果関係があるように思わせる。サイレントマジョリティを無視。データ、情報の一側面を過大に偏重して論じる。騙されないためのチェックポイントは、「結論ありきでないか」「主観的価値が混入していないか」「感情的迎合をしていないか」。 【統計は盗む】都合の悪いことは書かない。恣意的な問いや選択肢。運を実力と見させる。など、、、 2017/11/28
tacacuro
3
筆者によれば、統計はだまし(誤解を招く)、盗み(都合のいいように盗作する)、迫害し(中傷し偏見を招く)、殺す(左記が命にかかわる場合がある)という。被害に遭いたくなければ、「統計リテラシー」を身につけろ、と。すなわち、統計を用いてもっともらしく説明する他人の言説を鵜呑みにせず、5W1Hを頭に置きつつ、一旦否定して真逆の仮設を立ててみるなど、批判的に読むべきだと説く。統計のウソを暴くという形式を通じ、本書に散りばめられている、世の言説に対する筆者自身の「思い」を批判的に読んでみるのも面白いかもしれない。2017/10/27
-

- 電子書籍
- ふりだしから始まる覚醒者【タテヨミ】第…
-

- 電子書籍
- ハイテク戦争の特殊部隊 - 長編サスペ…