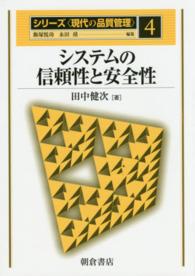内容説明
身体は人の感情や知性をつくりだしている。合気道家で医師の著者が解剖学にみる身体観の変化、身体知性でオープンダイアローグからべてるの家までを読み解く新たな「からだ」の話。内田樹氏との対談も収録。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ATS
12
★★☆小難しく書いてますが、内容はシンプルかなと思います。言語を中心とした科学(サイエンス)と非言語を中心としたアートの話で、科学だけでは不確実性が強い医療の世界ではやっていけない。そのためアート(経験や思考)が大切になってくるのだが、それは医療者の健康状態(感情や情動)に左右されやすく、それをコントロール(できればマネジメント)することが大切である。そのためには有酸素運動とかメタ認知の意識化などが有効であろうと。オープンダイアローグとべてるの家の例示はよくわからなかった。2017/11/07
まろすけ
9
これは当たり本。身体論、現在のネット社会でこそ輝きが増すと思う。⚫身体知性とは、分析が不可能な問題や、結末が不確かな未来について判断を下す時に機能する⚫医者が現場で行う『近道思考』、心理用語ではヒューリスティック⚫ソマティック・マーカー(内臓感覚)。身体を介して受け入れる感覚刺激が、感情(脳の機能)を作り出し、それが人間に意思判断決定を起こさせる⚫脳によって形成される自己とは、感覚器に絶え間なく与え続けられる情報に対して、反応(情動)を作る回路網に過ぎない。意思判断の源となる中枢は存在しない。コメント欄へ2018/09/22
ポカホンタス
5
著者は医師であり合気道家。ダマシオのソマティックマーカー説を詳しく紹介し、さまざまな状況判断には身体反応として生まれる感情が大きく関与していることを説く。内田樹との対談で、合気道の究極の目的は、出会うべき人と出会うべき時に出会える能力を磨くことだ、というくだりがあり、なるほどと思った。2018/03/11
スリカータ
3
小難しく書かれており、一般人には分かりにくい。内田さんとの対談の冒頭に著者がそれまでの総括を長々と語っているので、分かりにくさを感じた方は、対談だけ読めばいいかと思う。対談で印象深い点は、以下の通り。超長寿の人々は身体認知機能に長けている。自分の身体のどこがどの様に不調なのか言葉で語る力が秀でている。よく「身体の声に耳を傾けて」と言われるが、正にその通りなのだ。武術で身につくという、「必要な時に必要な人と出会う」武運とやらは、羨ましい限り。2017/11/20
ゆきの
2
少しとっつきにくかったけれど、おもしろかった。論理的思考だけで判断できないとき、もっと早い決断が迫られるとき、身体感覚による判断がある。ただし、感情や体調に左右される。オープンダイアローグは自問自答にもよいかも。いるべきときに、いるべきところにいて、なすべきことをなすのが武道。武道修練で滋養される一番大切な力は、コーリングを聞き取る力。2021/04/08
-
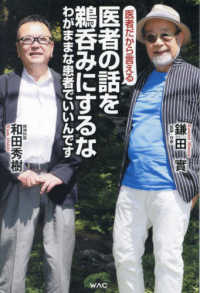
- 和書
- 医者の話を鵜呑みにするな
-

- 電子書籍
- 2023年の射手座の秘密を紐解く!