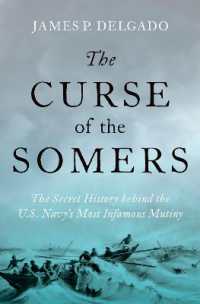内容説明
臨床40年の精神科医が、最も関心をもつネガティブ・ケイパビリティとは何か。せっかちに答えをもとめ、マニュアルに慣れた脳の弊害……教育、医療、介護でも注目されている、共感の成熟に寄り添う「負の力」について、初の著書。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ehirano1
293
「ネガティヴ・ケイパビリティ」という言葉を初めて知りました。ネガティヴを否定するのではなく、それも人生の一つだと受け入れ、そしてその何ともならないもどかしい中(懐疑、不思議、不確かさ)に居ることが出来る能力があるということを知ることが出来ただけでも僥倖でした。これだから読書はたまりません!読書万歳!!!2021/11/10
けんとまん1007
232
人は、どうしても答えを求めたがる生き物で、それは、人間の脳がそういう志向性があるからだということ。答えを求め、安心するということだろうと思う。ということは、安易に答えにしてしまう可能性も高い。果たして、それはいいのだろうか。そこを、我慢することで、より深みのあるものにたどり着ける。なるほどと思う。今の時代は、とにかくスピードを優先し、結果として短期的視点のものとなり、あとのことを考えない風潮が強い。ここで述べられている視点は、今後、ますます重要になる。2020/05/28
ネギっ子gen
130
悩める現代人が最も必要なものは「共感する」こと。この共感が成熟する過程で伴走し、容易に答えの出ない事態に耐えうる能力が、ネガティブ・ケイパビリティ。それは拙速な理解ではなく、謎を謎として興味を抱いたまま、宙ぶらりんの、どうしようもない状態を耐え抜く力。その先には必ず発展的な深い理解が待ち受けていると確信し、その場を耐え抜く。詩人・キーツが手紙の中に残した言葉を見つけ、ネガティブ・ケイパビリティの重要性を世に広めた精神分析医・ビオンは言う。<答えは好奇心を殺す>と。そう、謎は底の浅い答えよりも遥かに貴重。⇒2020/07/27
kaoru
120
精神科医である著者は「どうにも答えの出ない事態」に耐える力として「ネガティブ・ケイパビリティ」を提唱しキーツや医師ビオンを紹介、自らのクリニックの患者の例をも挙げる。問題設定が可能で回答がすぐに出る事柄は人生のごく一部で「残りの大部分は、わけがわからないまま、興味や尊敬を抱いて生涯かけて何かを掴み取る」のだと言う。本書を読んで漱石の『道草』の「世の中は片付かないことばかり」という一節を思い出した。人間には「片付かないこと」に耐える力こそ求められ、教育の現場にもその要素を取り入れるべきだという指摘は鋭い。⇒2021/06/12
ちゃちゃ
120
日々の暮らしや仕事の中で、私たちは容易に解決できない深刻な問題に度々直面する。先が見えずに苦しくて辛くて逃げ出したいと思うことがある。それでも、時には誰かに励まされ支えられながら、ずしりと重い荷物を抱えて歩く。歩いてゆくと少しずつ風景が変わり見えてくるものがある。そしてふと抱えた荷物が軽くなったことに気づく。ネガティブ・ケイパビリティー、答えを急がず持ちこたえていく力。何事も効率を最優先し迅速な問題解決を望む社会にあって、「宙ぶらりんを耐え抜く力」こそが生きる力となる。深く共感しながらの読書となった。2019/01/22