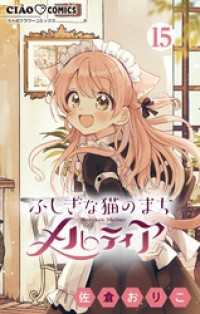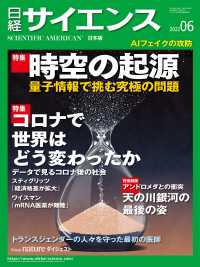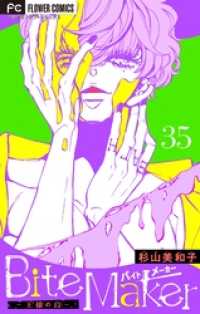内容説明
なにかと喧しい話題が多い沖縄。だが、日本と中国に挟まれたこれらの島々を「悲劇の島」や「栄光の琉球王国」という紋切型のイメージで見ると、その本当の姿を見誤る。国王即位を巡る後宮の陰謀、琉球史上最大の海戦の結末、離島を治めた女傑、最後の琉球王の淡い追憶など「アジアの交差点」といえる琉球諸島に生きた人々の足跡を、沖縄人二世の視点で辿る。「沖縄の戦後史」を新たに収録!
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
翔亀
37
【沖縄6】連続テレビ小説「ちゅらさん」を契機に沖縄ブームが起きたのが2001年。沖縄への移住者が続出した。その移住ブームを牽引したのがこの著者だ。沖縄2世(大阪生まれ)として移住し面白おかしい沖縄紹介本を書き続けた。そんな著者の沖縄史なので軽い導入としていいかなと思って読んだが、これが読み進めるうちにどんどんシリアスになってびっくりした。■琉球王国から現代までのエッセイ風通史。各章が史跡訪問から導入され、歴史エピソードを拾いながら語られる。これって、司馬遼太郎の「街道をゆく」を真似したのかな、まあ悪くは↓2021/10/20
リキヨシオ
28
基地問題や戦争時の沖縄戦に注目が集まるが、それ以前の沖縄の歴史を知る人は少ない。沖縄が辿った歴史を知ると沖縄が抱える問題の複雑さと根深さを痛感する。そもそも同じ沖縄でも沖縄諸島と先島諸島(宮古諸島・八重島諸島)では営む歴史や文化が全く異なる。琉球王国は明国への朝貢や東南アジアとの貿易で発展した独立国家だったが薩摩藩による侵攻で薩摩の支配下になり廃藩置県によって琉球王国は滅亡して沖縄県へとなった。明、薩摩、日本、米国、小国家・琉球が辿った支配と依存の歴史は現在の沖縄問題にも通じる所がある。結局何が正解なのか2017/10/25
coolflat
15
貝塚時代から沖縄戦までの沖縄の歴史。戦後についてはあとがきにて付け加える程度に表記。貝塚時代は、紀元前3世紀を境目として、貝塚時代前期と後期に大きく分けられ、おおむね前期が本土の縄文時代、後期が弥生時代に相当する。日本史と決定的に異なる特徴は、本土が弥生時代以降、古墳時代、奈良時代を経て平安時代へと変遷するのに対し、沖縄諸島(宮古諸島や八重山諸島を除く)では貝塚時代後期が10世紀前後、即ち本土の平安時代まで続いている点である。なお本土の弥生人との接触がみられる後期に至っても水稲耕作の跡は発見されていない。2017/09/25
piro
10
軽く沖縄の勉強をと思ったら、想定外に重く濃い内容で、沖縄の歴史について余りにも無知であった事を痛感しました。日本と中国の間でバランスを取ってしたたかに振る舞ってきた琉球王府は、いつの間にか依存体質が染み付いてしまった…現在日米の間で翻弄される沖縄にも通じる様に感じます。薩摩藩侵攻後の先島諸島における人頭税が明治36年まで続いた事、明治の王府廃絶後、先島諸島を清国領とする分割案があったと言う事は大きな驚き。そして同化政策により民族の自立心を喪失してしまったと言うくだりには心が痛みました。2017/08/19
雛子
10
帯を見て思ってたのと違ったけど、まさしく本音で語る沖縄史であった。明国や清国、薩摩の支配を受けた琉球王国時代から琉球処分、沖縄戦、戦後の沖縄。沖縄がいちばん幸せだった時代って、いつなんだろう。2017/07/08