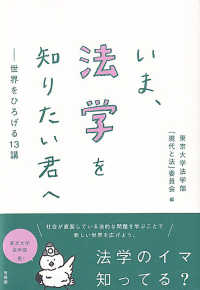内容説明
指針・要領に込められた思いがよくわかる。
子どもたちを取り巻く社会や世界の情勢が急速なスピードで変化する時代になりました。
この激動ともいえる時代で、私たちは子どもたちを育てています。この子たちの未来は大丈夫なのか、もっと時代に即した育ちが必要なんではないか、そう考えた欧米を中心とした国々は、国家戦略として子どもたちの幼児教育を考えました。
今回の「保育所保育指針」「幼稚園教育要領」「幼保連携型認定こども園教育・保育要領」の改定は、世界のそのような動きに呼応するものです。
本書は、「指針」と「教育・保育要領」の改定にかかわった汐見稔幸先生が、それらに込めた思いを、わかりやすく解説したエッセイです。
まず、対応が迫られている「環境・社会の変化」とはどのようなものかから説き始めます。それはすなわち世界が保育・幼児教育に投資する背景でもあるからです。
そして日本の現状はどうなっているかを伝え、それを踏まえて、3つの指針・要領がどう改定されたのかをくわしく説明します。
わかりにくい箇所は、イラストを多用して、できるだけやさしく解説します。読めば「なるほど、今回の改定の意味はこういうことだったのか!」と納得できる作りとなっています。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
7a
4
2017年度の保育所保育指針、幼稚園教育要領、幼保連携型認定こども園教育・保育要領の改定について解説する。OECDが定める次世代に必要な能力「キーコンピテンシー」=個人と社会の相互関係能力、自己と他者の相互関係能力、自律的に行動する能力。幼児期は非認知能力を高める教育をすべき。非認知能力=忍耐力、社会性、自信・楽観性。幼児教育における資質・能力の3つの柱=個別の知識・技能、思考力・判断力・表現力、学びに向かう力・人間性等。育ってほしい姿は卒園時に至るべきゴールではなくそこへ向かうようになっていること。2017/10/05
n___syu.
3
良かった。指針もう変わらない?2024/02/26
しまむらそらん
1
普段授業などで取り扱っている保育所保育指針、幼稚園教育要領、幼保連携型認定こども園教育・保育要領などで表現の仕方が違うことや明記されている内容のズレがどうして生じているのか書かれており、なるほどと勉強になった。特に非認知能力の育成が求められる現代では、「子どもの貧困」ついての課題が上がっており、経済的な貧困だけでなく体験の貧困や言葉の貧困などについて紹介されていた。法的な説明もイラスト付きで分かりやすく理解できた。2024/05/01
ぼちぼちいこか
1
保育の理想2019/03/20
かえるまーく
1
イラスト入りであること、わかりやすい言葉で書いてあることで、イメージしやすい。こういう風にやりたいなと思える一冊。2018/01/08