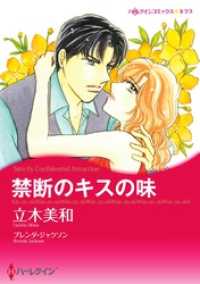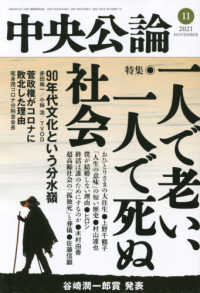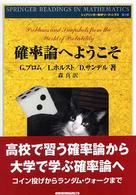内容説明
出版の中でも翻訳出版の世界はとりわけ奥が深く、また多様で複雑である。編集者として、児童文学作家として、翻訳者として、そして翻訳権エージェントの第一人者として……。戦争の余塵がまだくすぶる占領下から現在に至るまで、本の世界を縦横無尽に闊歩してきた著者が、翻訳出版史上の事件を自己の体験と綿密な調査からとらえ直すとともに、著者の周辺で活躍した個性豊かな出版人、翻訳者の素顔までを存分に描き出す貴重なエッセイ。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
タカラ~ム
5
翻訳出版における版権や著作権に絡んだ様々な事件を、長く翻訳出版に関する仕事を続けてきた著者が語る1冊。原著出版から10年経過したら自由に翻訳して良いとする「10年留保」の話とか、戦後GHQ(というかアメリカ)に押し付けられた条件とか、今の日本の翻訳出版で権利関係がしっかりと管理されている礎が、こうした過去の事件の教訓によるものなんだとわかった。題材は堅苦しいけど、書かれているエピソードは興味深いものなので、けっこう読みやすいです。2017/09/24
at
1
昔、翻案物の小説を読んでいたんだなあ。2025/03/23
よだみな
1
著作権や翻訳権の勉強に読んだ。つらい。プロがこんなに右往左往しているのだから、素人のわたしができるわけがないという感想にいたった2024/08/02
あらい/にったのひと
1
昭和の翻訳に関する出来事の記録なんだけど、なんというか村の古老による伝承みたいなもので、端々に年輪を感じさせるすごい本。いやー今みたいに簡単に海外と連絡取れなかった時代、翻訳に限らず許可を取るのは大変だったろうなあ、という。あと、本文と挿絵で著作権の保護期間が変わるというのは言われたらなるほどで、これは大変ですね…個人的には挿絵は随時変えていいし、再話や抄訳でもありなんではないかな、と思っています。具体的には私が読んだ奇巌城も後ろ切れてたし、水滸伝も70回本だったからね。2024/04/14
てまり
1
「昔は著作権なんて気にせずどんどん訳してたんだよ!」という通説を覆さんとする本。たとえば戦前だと、アメリカのものはそもそも許可なしで翻訳自由、それ以外も出版から十年たてば自由で、その気軽さは現代と全く違いますが、しかしながら出版直後に話題書を翻訳したい場合などに熱い情熱を持って著作者とやりたりした話などがあり、勉強になります。またその状況も終戦によって変わったとのこと。欧米との力関係の変化を、おそらく情報が行き来しやすくなったことによって、以前出版のものまで遡ってさまざまな処置が必要だったと。単に条文に→2021/01/08