- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
過労や長時間労働が問題となっている今、苦痛を伴わずに、脳を休息させながら仕事のパフォーマンスを上げる方法が求められている。疲労を防ぐ、脳の「トップダウン処理」、「メタ認知」という情報処理能力、「ワーキングメモリ」を生かして仕事の効率を上げる方法、人間関係のストレスへの具体的な対処法など、“疲れずに仕事をする方法”を丁寧に解説する。疲労のメカニズムを科学的に解説した第一弾、食事・睡眠・生活環境での疲労予防や解消法を具体的に示した第二弾につづく、『すべての疲労は脳が原因』シリーズの第三弾。 【目次】はじめに 脱脳疲労で仕事を効率化する/第一章 疲れない脳を作る/第二章 疲れない脳を作る鍵は「記憶」にあり/第三章 疲れを溜めない働き方を身につける/第四章 ビジネスシーンで脳疲労を予防する方法/第五章 職場で疲れない人間関係を築く/第六章 脳疲労とストレス・不調の深い関係/おわりに
目次
はじめに 脱脳疲労で仕事を効率化する
第一章 疲れない脳を作る
第二章 疲れない脳を作る鍵は「記憶」にあり
第三章 疲れを溜めない働き方を身につける
第四章 ビジネスシーンで脳疲労を予防する方法
第五章 職場で疲れない人間関係を築く
第六章 脳疲労とストレス・不調の深い関係
おわりに
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
koheinet608
16
著者曰く、自律神経も筋肉と同じように発揮できるパワーの上限は決まっていると。これは年齢と共に落ちていく。20代と比べて30代は8割ほどになり、40代になると半分ほどになる。拡大解釈すれば、同じ20代の疲労では、30代では1.26倍、40代では1.87倍になる。最近、「疲れやすくなった」と自覚している人は、単純に言えば「すること」が多いからだろう。年齢を重ねると共に「すること」を厳選して行い、決して無理をしない、ただ日本でこれを実現するのは極めて困難だと思う。 2018/12/10
Francis
14
シリーズの2は飛ばしてこの3を先に読む形になった。40歳以上の人間は自律神経の機能が若いころに比べると低下してくるので疲れやすくなる。ではどうしたらいいのか、を説明。仕事では60パーセントの力で70パーセントの結果を出すようにすべきだが、日本の今の働き方は「お疲れ様でした。」のあいさつにみられるように100パーセントの力を出し切ることが求められているので、これを変えるべきである、などの鋭い指摘がなされている。今行われようとしている「働き方改革」もこの本に書かれていることを参考にする必要がありそうだ。2017/10/18
デスカル
11
▼タスクを付箋にして、毎朝5分で作り、終わったら捨てる。体調により、こなす数を変える▼100%の力で100%以上は無理なので、60%の力で70%を目指す。得意分野なら可能▼「飽きた」は脳疲労のサインなので休む▼負荷が大きい日の飲み&運動は❌。早く寝ること▼脳の潜在能力(経験値)の現れが直感なので、従ってみるかなぜそうか考える▼物事を俯瞰、客観視するメタ認知を鍛えると脳も鍛えられる▼短時間で休むには目を閉じ机に伏す(視覚情報を遮断)▼オープンスペースよりもパーテーションで仕切りを作りパーソナルスペースを確保2018/06/03
ピンガペンギン
9
図書館。ざっくりと読んだだけだが、いい意味で要らない力が抜けるような内容で、読んで良かった。(この医師を知ったきっかけはコンビニの本だった。今でも売ってるかも。)最後のほうに脳の俯瞰的なある認知能力を鍛えるには、直に生の出会いをする必要がある、とあり、コロナ禍で生徒、学生さんの経験を様々大人が奪ってきたことを思いました(Go to EatやらGo to travelはやっておきながら)。2022/10/03
こじみき
8
シリーズ最終版。社会人の自分には本書が最もためになりました。テクニックが多く書かれてますが、一番印象的なのは常に全力はもたないよということ。適度に手を抜くことは悪いことではない。継続的に働き続けるために非常に重要なこと。学生とは違うなあと感じます。あの頃は常に全力で結果もついてきたのに社会人はなぜそうもいかないのだろうか?責任の度合いや組織の違い?いずれにせよ、健康で働き続けるために疲労は溜めないようにします。手を抜くとこは絶対に抜きます。ほどほどに。悪いことではないと自分に言い聞かせて…
-
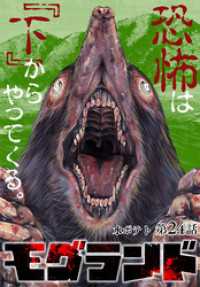
- 電子書籍
- モグランド 分冊版 第24話 ゼノンコ…
-
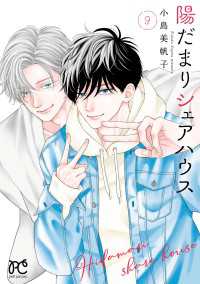
- 電子書籍
- 陽だまりシェアハウス【電子単行本】 9…
-

- 電子書籍
- ライブダンジョン!【分冊版】 4 ドラ…
-
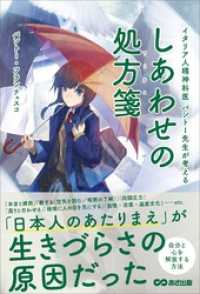
- 電子書籍
- しあわせの処方箋(Tips)~イタリア…
-

- 電子書籍
- 悪罪 (2)




