内容説明
中世は、決して暗黒期ではない。中世とルネサンスの間に、断絶はない――。ルネサンスは1400年代(クァトロチェント)のイタリアより前、12世紀にはすでにさまざまな形で現れていた。ギリシア・ローマ文化を破壊、封印した陰鬱な時代、と捉えられがちな「中世」の真実を、ラテン語復権、大学の誕生などの事蹟から明らかにしてゆく中世の歴史的位置づけを真っ向から問い直した問題作。
目次
はしがき
第一章 歴史的背景
第二章 知的中心地
第三章 書物と書庫
第四章 ラテン語古典の復活
第五章 ラテン語
第六章 ラテン語の詩
第七章 法学の復活
第八章 歴史の著述
第九章 ギリシア語・アラビア語からの翻訳
第十章 科学の復興
第十一章 哲学の復興
第十二章 大学の起源
原 注
解 説
原本あとがき
文庫版あとがき
文献書誌
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
吟遊
14
ハスキンズ、原著は1927年。いまだに読み継がれるのは、テーマごとにコンパクトにまとめられていること、テーマ(法学、大学、科学…)の取り上げ方が幅広く、きちんと目配り利いていること、が理由かな。ラテン人名がたくさん出てきて、知らない人も多いので、それぞれにちょっとした解説がほしいが、そういうものはない。該博な語り。2017/09/18
Copper Kettle
7
暗黒時代と思われている中世の12世紀に起こった古典の復活を取り上げる。中世は一神教のキリスト教に塗りつぶされて、聖書の中に書かれていることが真実とされていたので、古代ギリシアの哲学者たちが観察や経験をもとに考察した研究成果は忘れ去られていたので、12世紀にそれらの書物がイスラム他経由で復活して批判的精神を育んだとされる。興味深かったのは、ラテン語は聖職者の間で使われ続けていたけれど、そもそもは古代ローマ、つまり多神教時代の人たちの言葉であるところに複雑な葛藤が聖職者たちにあったという指摘は新しい視点だった2022/07/19
てれまこし
7
ヨーロッパ近代の曙をイタリア・ルネサンスに求めるのはもう古いらしい。国家、教会、大学なんて今日も重要な組織が形成されたのは十二世紀。細々と続いていたラテン語文化の遺産が取りもどされるのも十二世紀。それもギリシア語やアラビア語からの翻訳によってである。そうかと思えば、アリエスや阿部勤也などによれば、キリスト教的な世界観、死生観が民衆に浸透するのも同じ時期である。偶然か否か、同じ時期に日本でも柳田国男などが中世に注目してる。やはり近代を古代に直接結びつける「昨日がダメだから一昨日主義」に反発したのであった。2020/03/28
さとうしん
7
中世の各分野の学術や文芸のありようをまとめ、イタリア・ルネサンス以前に「知的復興」が進められていたことを示す。ラテン語が国際語としてだけではなく「自国語」の役割も担い、各地域でなまりや新しい慣用を生み出した「生きた言語」であったという指摘が印象に残った。2017/11/10
馬咲
6
今や中世は近代の基礎の形成期として再認識されているが、本書はその契機となった一冊。古典の収集・整理の有り様、ギリシア文献の翻訳事情、「大学」の誕生に至る教育文化の変遷等を通して、中世の「学問の復活」に焦点を当てている。表題は、12世紀が中世で最も知的活動が実り豊かな時代だったことを意味するが、そこには新たな創造の前の下準備、古典の抜粋と模倣が主流な前世紀までの知的動向との連続性が踏まえられている。中世ラテン語というと形式張った「聖」の印象だが、すでに各地で方言化していたほど、世俗に縁のある言語だった。2024/10/16
-

- 電子書籍
- 訳あり令嬢の法廷【タテヨミ】第35話 …
-

- 電子書籍
- この世界がゲームだと俺だけが知っている…
-

- 電子書籍
- 【フルカラー】悪役令嬢の発情期【タテヨ…
-
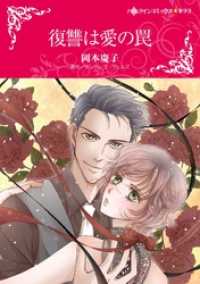
- 電子書籍
- 復讐は愛の罠【分冊】 1巻 ハーレクイ…





