内容説明
生徒の「自主的、自発的な参加」に基づく部活動。それはこれまで、「部活動を通した成長」「能力の向上」「友だちとの深い結びつき」など、教育的な文脈で語られてきた。
しかし、統計データや教師の声を繙いていくと、「子どもの成長のため」を免罪符に、大きな矛盾や教員の負担が覆い隠されていることが明らかになる。
教育課程外の活動である部活動は、本来教員の業務ではない。にもかかわらず、「教師が部活顧問をするのは当然」と見なされ、強制的に割り振る学校が大半。早朝から夜まで、土日も休まず活動する部活は多い。日本中の学校で行われている部活動のほとんどが、教師がボランティアで行う「サービス残業」に他ならない。
また、自主的な活動であるはずの部活動への「全員加入」を強制する、自治体・学校も決して少なくない。
法的・制度的な位置づけが曖昧なのに、子ども・教師の両方が加入を強制され、そのことに疑問を抱かない。保護者も「当然のもの」として教師に顧問として長時間の活動を求める。そのような部活動のモデルで成長していく子どもは、このような部活動のあり方を当たり前に思い、再生産していくことになる。
「教育」「子どものため」という題目の裏で何が起きているのか。統計データや子ども・教師の声の解釈から、部活動のリアルと、部活動を取り巻く社会の構造が見えてくる。ほんとうに自発的で、過度の負担のない部活動へ向かうための、問題提起の書。
●部活の加熱化を示す大会数増
●部活動は教師のやりがい搾取?
●「自主的な活動」なのに全員強制
●顧問の「無償奉仕」を求める保護者
●週三回でも「部活動の教育効果」は見込める!
目次
はじめに
1 部活やめたい
2 生徒だけでなく先生も
3 部活は楽しい!:「強制」と「過熱」から考える
4 本書の諸前提:「エビデンス」と「4つの基礎的視座」から運動部・文化部をよりよいものに
第1章 「グレーゾーン」を見える化する
1 「なぜ廊下を走るの?」中学生の訴え
2 「自分だけ外を走ればいい!」
3 「グレーゾーン」としての部活動
4 無法地帯のさまざまな問題と矛盾
5 部活動は「教育課程外」の活動
6 「授業」とのちがいから「部活動」を理解する
7 「スポーツクラブ」や「学習塾」とのちがいから「部活動」を理解する
第2章 自主的だから過熱する――盛り上がり、そして降りられなくなる
1 学校はトップアスリート養成機関?
2 東京オリンピックはもっと盛大に:勝つことに対して高まる期待
3 理想と現実のギャップ
4 部活は麻薬
5 10年間で部活動の指導時間が突出して増加
6 組み体操の巨大化と部活動の過熱との共通点
7 自主的だから過熱する
8 部活動に全国大会がなかった頃
9 部活動が「評価」される 過熱の背景にあるもの
第3章 自主的なのに強制される――矛盾に巻き込まれ、苦悩する
1 大きな勘違い
2 生徒の強制入部
3 部活動指導は教員の仕事なのか?
4 実現不可能な職務命令
5 「居場所」の論理と「競争」の論理:部活動の存在意義は「機会保障」にある
6 競争の論理の見えにくさ
【COLUMN】Twitter発、世間を動かした「部活動の正論」
第4章 強いられる「全員顧問」の苦しみ
1 土日も出勤:「早く負けてほしい」
2 自主的に土日がつぶれていく
3 「部活未亡人」:過労を嘆く妻たちの声
4 若い先生たちの過重負担
5 全員顧問「制度」とは?
6 全員顧問制度の拡大とその背景
7 部活動で先生が「評価」される
第5章 教員の働き方改革――無法地帯における長時間労働
1 教育は無限、教員は有限
2 在校12時間 多くが「過労死ライン」超える
3 休みなき教員の一日
4 一日の休憩時間はたったの10分
5 先生には夏休みがある?
6 夏休みも残業、土日出勤
7 労働基準法の「休憩時間」が確保されていない違法状態
8 無理矢理の休憩時間設定
9 教員の半数は「休憩時間数を知らない」
10 諸悪の根源「給特法」
11 休まないことが美化される!?
【COLUMN】部活動の法的根拠を探るなかで見えてきたこと
第6章 素人が顧問
1 未経験顧問が雪崩に巻き込まれて死亡
2 ボールにさわったことがあればOK
3 素人顧問が語る苦悩
4 部活動好きだった先生の挫折
5 次善の策として顧問を引き受ける
第7章 過剰な練習、事故、暴力――苦しむ生徒の姿
1 守られなかった「週2休」の指針
2 文科省が本気を出した
3 生徒の部活動時間:最大は千葉県の1121分/週
4 外部指導者は救世主か
5 外部指導者は生徒の負荷を増大させる?
6 部活動を「やめさせない」圧力
7 「内申」という束縛の欺瞞
8 部活動における事故
9 顧問からの暴力
【COLUMN】 スポットの当たりにくい小学校の部活動
第8章 先生たちが立ち上がった!
1 職員室の当たり前を打ち壊す
2 「部活問題対策プロジェクト」の誕生
3 既存の組合を超えた活動
ほか
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
きみたけ
たまきら
ま
マッキー
Riopapa
-
![改訂版 キクジュク【Basic】大学入試レベル[音声DL付]](../images/goods/ar2/web/eimgdata/EK-1661326.jpg)
- 電子書籍
- 改訂版 キクジュク【Basic】大学入…
-
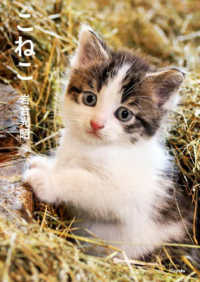
- 和書
- こねこ 写真文庫






