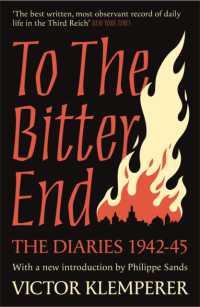内容説明
名字には日本人と一族の歴史が隠されている。
日本には10万とも20万ともいわれる名字がある。それだけ世界に類を見ない数の家系が受け継がれてきたことを意味する。古代豪族の末裔、地形・地名由来、職業由来など、名字ひとつで先祖が生きてきた土地や生業が推測できる。
バラエティ豊富なことで、名字に関する誤解も多い。例えば、「江戸時代以前は武士以外に名字はなかった」というもの。学校でそう習ったという人も多いが、事実は「武士以外は名字を“名乗ること”が許されなかった」だけ。遅くとも室町時代には庶民が名字を持っていたことを示す文献も残っている。
もう1つの誤解は、図書館の分厚い名字事典に関係する。それらには何万もの名字が収録されているが、大半は家系図などが残されている武家、公家、名家のもので、国民の9割を占めた農民、町民のルーツはほとんど示されていない。「藤」が付く名字のすべてが藤原氏の末裔ではないのである。
庶民の名字を研究してきた第一人者であり、NHK番組「日本人のおなまえっ!」のコメンテーターとして知られる著者は、本書で約2500の名字のルーツを解説した。これを読めば、ほとんどの日本人が自分のルーツの一端を知ることになるだろう。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
tomi
35
サブタイトルと装丁だけ見ると代表的な名字を扱ったよくあるハウツー本のようだが、多くの名字の由来のルーツを探る、名字研究の第一人者による結構本格的な本。300位までの名字ランキングや都道府県別のベストテンも掲載されているが、新旧字体や異体字は原則同じで読み方の違いは別に作成されている。以前出た名字ランキングの本では、旧字が別に集計されているのが疑問だった。著者によるとこれは先祖が戸籍にどの字を書いたかの違いで、書き間違いも多く名字のルーツには全く関係がないそうである。2017/12/02
たまきら
23
夫の名字は日本で2番目に多いんですが、私の旧称は上位300にはいないうえ、母の名字に至っては奄美の小さな島出身の祖父なので、本にも出てこない始末。オタマガッカリ。名前も面白いけれど、どこの国に行っても馴染み、どこの国の博物館にもよく似た復元模型がある原人顔の夫の骨格の由来に興味が尽きない。…ふしぎだなあ。2017/10/06
めい
5
普段はあまり意識しないけど、名字には色々な奥深い歴史やルーツがあるんですね。 これだけたくさんの名字があるのも日本の大切な文化。 目先の損得に流されて簡単に損なってはいけないものだと思う。2025/09/21
smatsu
4
軽い感じの装丁に似合わぬ良書。類書では武光誠の『日本の名字』も良い本でしたが、本書も良い。歴史的俯瞰的な日本人の氏、姓、名字にかんする経緯も説明し、個別の名字についても豊富な情報が目配りよく整理されていて素晴らしい。著者のこのテーマへの熱意と研究の深さが読んでいて自然と伝わってくる。長谷川や渡辺のルーツは一つしかないとか、「さいとう」の文字は85種類もあるとか、ネタとしても面白い話がてんこ盛り。普通の本は読み終わったら図書館に寄贈したり中古屋に売ってしまうが、これは本棚にずっと置いておきたい本です。2023/09/08
乱読家 護る会支持!
4
学校で習った「江戸時代に武士以外は名字がなく、明治になって急に名字を名乗った」は間違い。「江戸時代には武士以外は名字を名乗ることが出来なかった」が正解で、ほとんどの人は名字を持っていた。 そもそも、武士と農民は同祖であり、室町時代に農民は名字を持っていた。 長谷川のルーツは奈良県桜井の初瀬川。佐々木のルーツは、近江の地名。渡辺は、大阪中之島の「渡しの辺り」。青山、内藤は大名。地形、風景に由来する、山本、山下、山根、山崎、林など。水わまりの地形から、沢田、滝川、泉。鈴木は熊野由来の「稲の乾かし方」2017/12/06
-

- 電子書籍
- 君の悪夢、美味しくいただきます【タテヨ…
-

- 洋書
- Overcoming