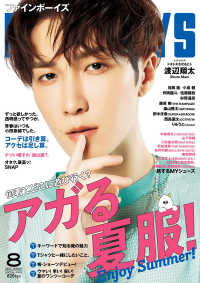内容説明
中島岳志氏、開沼博氏が推薦!
「平和」は、なぜ口にするのが気恥ずかしい言葉になったのか。それは「平和」と対になる「戦争」に、明確なイメージを持ちにくくなったこととも関係している。記憶の風化に加え、対テロ戦争に象徴されるように戦争そのものが変質しているなかで、「平和」という言葉も「戦争」という言葉も、機能不全を起こしているからである。
では現在、その語り方をどのように「更新」していくことが可能か。石原慎太郎、色川大吉、江藤淳、大江健三郎、大塚英志、小田実、高坂正堯、小林よしのり、坂本義和、SEALDs、清水幾太郎、鶴見良行、西部邁、野坂昭如、福田恆存、丸山眞男、三島由紀夫、山口瞳、吉田茂……。本書はそのヒントを探るために論壇での議論に重点を置きつつも、文学やポピュラー文化にまで視野を広げ、戦後日本「平和論」の正体に迫る。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ケー
11
戦後70年という非常に長い期間を「平和」というキーワードで読み解いていく筆者。抽象的なテーマでも大きな幹を発見し、丁寧にまとめる力量は見事。論文ではないので、筆者の態度がやや強めに表明されている。若干専門的な話もあり、タイトルの割には難しいかもしれないけれど、コンパクトに通読できるという意味で貴重な一冊。2016/11/19
樋口佳之
4
84年生まれ、2016年現在30代に入ったばかりの著者。90年代の小林よしのりの大活躍(?)さえ実体験してるかどうかでしょ。自分は80年代位から記憶として思い出せるのだから、なんかすごい隔世感。/「平和」の空洞化への危惧はよくわかりました2016/09/07
takuji
0
平易な文章で書かれていてとてもわかりやすい。 戦後を振り返りながら政治家、学者、ジャーナリスト、作家たちの主張を取り上げ、「平和」の意味の変遷をたどる。 注釈や参考文献に挙げられている資料も個人的にとても興味深い。 私レベルにはぴったりの良本。2016/09/01
-
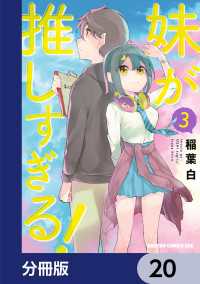
- 電子書籍
- 妹が推しすぎる!【分冊版】 20 ドラ…
-

- 電子書籍
- 富士山さんは思春期 5 アクションコミ…