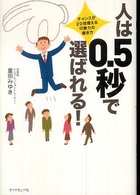- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
政党政治を生み出し,資本主義を構築し,植民地帝国を出現させ,天皇制を精神的枠組みとした日本の近代.バジョットが提示したヨーロッパの「近代」概念に照らしながら,これら四つの成り立ちについて論理的に解き明かしていく.学界をリードしてきた政治史家が,日本近代とはいかなる経験であったのかを総括する堂々たる一冊.
目次
目 次
序章 日本がモデルとしたヨーロッパ近代とは何であったか
第一章 なぜ日本に政党政治が成立したのか
1 政党政治成立をめぐる問い
2 幕藩体制の権力抑制均衡メカニズム
3 「文芸的公共性」の成立──森鴎外の「史伝」の意味
4 幕末の危機下の権力分立論と議会制論
5 明治憲法下の権力分立制と議会制の政治的帰結
6 体制統合の主体としての藩閥と政党
7 アメリカと対比して見た日本の政党政治
8 政党政治の終わりと「立憲的独裁」
第二章 なぜ日本に資本主義が形成されたのか
1 自立的資本主義化への道
2 自立的資本主義の四つの条件
(1)政府主導の「殖産興業」政策の実験
(2)国家資本の源泉としての租税制度の確立
(3)資本主義を担う労働力の育成
(4)対外平和の確保
3 自立的資本主義の財政路線
4 日清戦争と自立的資本主義からの転換
5 日露戦争と国際的資本主義への決定的転化
6 国際的資本主義のリーダーの登場
7 国際的資本主義の没落
第三章 日本はなぜ、いかにして植民地帝国となったのか
1 植民地帝国へ踏み出す日本
2 日本はなぜ植民地帝国となったか
3 日本はいかに植民地帝国を形成したのか
(1)日露戦争後──朝鮮と関東州租借地の統治体制の形成
(2)大正前半期──主導権確立を目指す陸軍
(3)大正後半期──朝鮮の三・一独立運動とそれへの対応
4 新しい国際秩序イデオロギーとしての「地域主義」
(1)一九三〇年代──「帝国主義」に代わる「地域主義」の台頭
(2)太平洋戦争後──米国の「地域主義」構想とその後
第四章 日本の近代にとって天皇制とは何であったか
1 日本の近代を貫く機能主義的思考様式
2 キリスト教の機能的等価物としての天皇制
3 ドイツ皇帝と大日本帝国天皇
4 「教育勅語」はいかに作られたのか
5 多数者の論理と少数者の論理
終章 近代の歩みから考える日本の将来
1 日本の近代の何を問題としたのか
2 日本の近代はどこに至ったのか
3 多国間秩序の遺産をいかに生かすか
あとがき
人名リスト
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
遥かなる想い
樋口佳之
Shoji
1.3manen
skunk_c
-
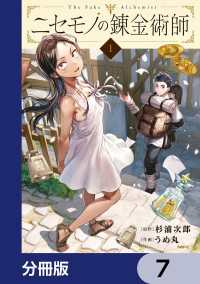
- 電子書籍
- ニセモノの錬金術師【分冊版】 7 MFC
-

- 電子書籍
- 嫌われ魔女は英雄に愛される【タテスク】…
-

- 電子書籍
- 恋は双子で割り切れない2 電撃文庫
-
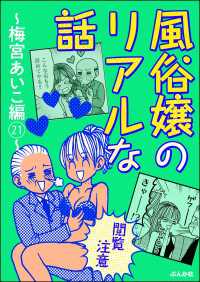
- 電子書籍
- 【閲覧注意】風俗嬢のリアルな話~梅宮あ…