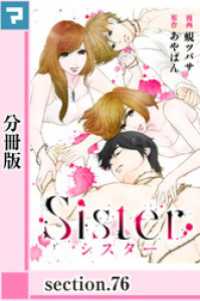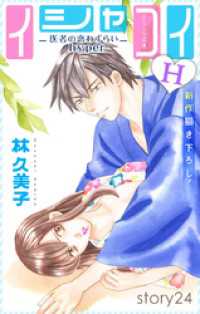- ホーム
- > 電子書籍
- > ビジネス・経営・経済
内容説明
<p>■インテル、ナイキ、日産、リクルート……有力企業が続々導入する「学習する組織」、初の入門書!
■世界250万部突破のベストセラー『学習する組織』をもとに、日本における第一人者が、実践を意識してわかりやすく解説</p><p>【人と組織の未来は、「学習能力」で決まる】</p><p>MITで生まれた、人と組織の能力開発メソッド「学習する組織」。
「個人の成長」と「組織の成長」を相乗的に実現するノウハウを、
日本における第一人者がわかりやすく解説したのが本書です。</p><p>「学習する組織(ラーニング・オーガニゼーション)」とは、
変化に柔軟に適応し、進化し続ける組織のこと。
通常のPDCAを超える「ダブル・ループ学習」を実践し、
「志を育成する力」「複雑性を理解する力」「共創的に対話する力」を
培うことで、個人・チーム・組織の持続的成長を実現します。</p><p>【自分・チーム・組織を成長させる5つの道を、事例と演習で学ぶ】</p><p>行動科学・心理学・リーダーシップ論など幅広い知見に基づく
この理論を初めて紹介したピーター・センゲ著『学習する組織』は
世界17ヶ国で出版され、250万部を超えるベストセラーに。
変化が激しく、常に革新が求められる今日のビジネス環境において、
人と組織の問題を考える上でのバイブルとして世界各国の
ビジネスリーダーに読まれています。</p><p>『「学習する組織」入門』は、そのエッセンスを伝える入門書です。
学習する組織の柱となっている5つの「ディシプリン」を
ひとつずつ丁寧に解説。イメージのしやすさ、実践しやすさを
意識して、各章に「事例」と「演習」を掲載しています。
また実践する上で直面しがちな課題もカバーした上で、
「U理論」など最近のマネジメント思想の潮流も踏まえながら、
組織とリーダーシップの未来像を展望します。</p><p>第1章 学習する組織とは何か
第2章 組織の学習能力 ― 学習サイクルと学習環境、そしてディシプリン
第3章 自己マスタリー ― 自分の意識と能力を高め続ける
第4章 システム思考 ― 全体像をとらえ、本質を見出す
第5章 メンタル・モデル ― 前提を問い、認識を新たにする
第6章 チーム学習 ― 場と関係性の質を高める
第7章 共有ビジョン ―「どうありたいのか」に答える
第8章 実践上の課題と対策
第9章 組織の未来、リーダーシップの未来</p>