内容説明
「クジラの研究者になるのもいいな」小笠原から極北アラスカ、そして南太平洋バヌアツへ。嗅覚をキーワードに、クジラの進化を追いかけた。
本シリーズは、生物進化の分野に興味を抱く若い学生の皆さんにまず読んでいただきたい。本シリーズは、それぞれの【著】者がなしとげた研究成果という最終産物だけでなく、そこにいたる道筋が描かれている。これから進化の研究をめざす人々にとって、これらの内容はとても参考になるだろう。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
yooou
4
☆☆☆☆★ 鯨、陸上に上がった生物が再び海に戻った物語を嗅覚の痕跡から辿る予想外の旅は波乱万丈で面白いことこのうえない。小ぶりな本ながら鮮やかな読書体験を残す良書でありました2016/04/25
Tsukasa Fukunaga
1
陸上に進出した哺乳類は、水中ではなく空気中の化学物質を検出する方向へと嗅覚受容体遺伝子が進化して行ったが、その後再び水中へと戻ったクジラではこれらの遺伝子・嗅覚機能はどうなっているのだろうか、という研究について述べられた本。感覚能力の相互補完についての新説提唱なども含め、個々の研究は面白いが、まだ研究の中途段階という印象が強い(例えば、ウミヘビのゲノムを読みたいみたいな話でウミヘビの話が終わるなど)捕鯨倫理の問題でrejectを食らう話は(非常に気の毒だとは思うが)興味深い話であった。2016/05/02
Masaki
1
クジラにおける嗅覚の進化(というか退化)を、遺伝子レベルで解析した研究について書いた本です。マッコウクジラなどのハクジラ類では、そもそも嗅覚を持っていないそうです。ヒゲクジラ類では、脳にある嗅球の背側領域が存在せず、おそらくは進化のの過程で、陸から海に適応するどこかで失ったのだろうとのことです。このあたりのことを、ゲノムの解析を行って明らかにしていく過程を書いてますが、ちょっと難しい。面白いことは面白いんですがね。2016/03/28
ヤナセトモロヲ
0
★★★2017/03/16
YK
0
深くなるほどロドプシンの最大波長は短くなる植物プランクトンが捕食される際にジメチルスルフィドが放出される その匂いを手がかりにする非同義置換率/同義置換率 でその遺伝子の重要度がわかるバヌアツアオマダラヘテロ接合がおおい=遺伝的多様性が高い2014年3月の国際司法裁判所による判決 日本の調査捕鯨はだめ(6年で2本しか査読論文がでてない) 環境変化により失われる遺伝子の解析は面白い 植物ではどうか?2016/08/28




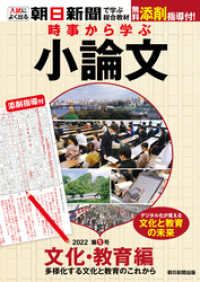
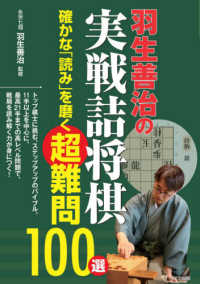
![デザート 2017年 1月号 [2016年11月24日発売]](../images/goods/ar2/web/eimgdata/EK-0373983.jpg)


