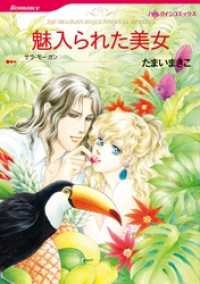内容説明
赤ちゃんはコミュニケーションの達人だ。なんでも吸収し人間関係に悩まされることもない。翻って、私たち大人は? 「平均の魔法」にかけられたように均質を求めすぎる私たち。しかし、限界のある能力をより効率的に使うために不要なものを切り捨てることこそが人の「発達」なのだ。だからこそ無限の「個性」が生まれる。赤ちゃんの研究から見えてきた、「個性」の本質と成り立ち、そしてポジティブな人生を送る方法。
目次
はじめに ~赤ちゃんから個性を知ろう
1章/コミュニケーションを赤ちゃん時代から考える
2章/個性はいつどのように生まれるのか
3章/環境と心の関係を見直す
4章/私たちを形づくる「食生活」を考える
5章/コミュニケーションの本質と個性
終章/赤ちゃん学と個性を振り返る
あとがき
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
のり
5
個性を認めることは難しいが、他人の個性を正しく見ることは、自分自身を正しく知ることにもつながる。身の回りの環境を把握、整理して、赤ちゃんの個性を伸ばす環境づくりをすることが、今生きる環境とその未来をあらためて知るきっかけとなる。赤ちゃんの研究が数十年に渡ってたくさんの国で行われていることがわかりました。街並み、におい、食、関わる人の表情など、さまざまな環境が赤ちゃんへの成長発達に関わってくる。環境を整えることが重要。2014/09/30
Michio Kubota
3
人が生まれてから今までの歴史=個性であり、それは獲得と同時に捨てることの連続だということがよくわかる本。個性はことのほか差異が大きく、多いことを認識することが、コミュニケーション上重要ですね。2014/10/14
ゆうちゃん
2
赤ちゃんは新奇性を選好し、歳をとるにつれて習慣に根差し選好するようになる。なぜ、人はファストフードを好むのか、においを嗅ぐことは羊水にいるときから始まる、など興味深いテーマがあって面白かった。ただ肝心の個性そのものにはあまり触れられてなかった。2014/08/23
Friedrich Nietzsche
0
人間の社会性や認知機能は底知れない凄さがある。赤ちゃんの頃からその片鱗を見せているんだといったことが書かれてある本2015/04/14
ちゃすくん
0
これから調べたい内容を次々と発見できる本だった。→匂いの仕組み、腸内にある味覚受容体の働き、男女の好む色の違い、サヴァン症候群のような個性、視覚野の麻痺が点字の読み取りに影響する、背側経路と腹側経路による見え方の違い、4歳前後からの既知選考2022/05/28