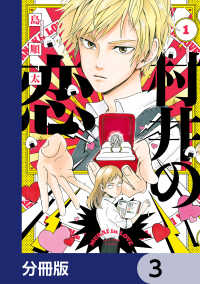- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
ユーラシア大陸の正反対に位置にある日本とイギリス。新石器時代、大陸では四大文明の地域のような「文明型」の社会が広まっていくなか、その果てにあった両地域では、「非文明型」の社会へと発展していった。直接的な交流がないこの二つの地域になぜ共通性が生まれたのか? また、同じホモ・サピエンスなのに、なぜ大陸とは異なる方向へ進んだのか? ストーンサークルや巨大な墓など、それぞれの遺跡を訪れることで、いままで見えてこなかった知られざる歴史に迫る。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
姉勤
25
縄文とケルトとのタイトル通りの内容ではなかったが、 日英の遺跡ガイドブックとしては有用にアクセスと見所に触れている。有史最古にブリテン島に渡ったとさせるケルト民族以前の、前ケルト、原ケルトと仮称する人類がストーンサークルや環状遺構をつくり、それと似た様な縄文の遺構が日本列島に。ユーラシアの西と東での類似性は、これも同様に金属を発明した、大陸中央からの文明の流入で変質せざるを得なくなるが、塗り変わったイギリスと混ざり合った日本の差異を見出す。なかば強引なところもなくはないが、楽しめた。2019/07/12
Porco
24
イギリスの考古学について、初めて読みました。地味なテーマなのに、なかなか読ませる。2017/10/09
funuu
22
地球という重量環境の中で進化した私たち人類「ホモ・サピエンス」は、大きくて重たいものが小さく軽いものよりも上方にあるのを目にしたとき、等しく不安感を覚え、その背後に「力」を連想する。認知心理学では、このような生得的身体感覚に根ざした心の動きを「イメージ・スキーマ」という。「パワー・スポット」の形態はこのイメージ・スキーマによる心の動きと密接に関連している場合が多い。石器時代は石器を作れる者に富が集まった。現代は核兵器最新兵器を持つ者に富は集まる。石斧を持って何かを破壊する感覚とい原爆を落とした感覚は同じ。2017/09/21
おせきはん
9
日本と英国の新石器時代の遺跡を巡り、両者を比較しています。同じように発展していきながら、その後、大陸との距離の違いから、外からの影響を受ける度合に差が出てきました。両者に接点は全くなかったはずですが、環境が近いと同じようなことを考えるものですね。2017/06/24
びっぐすとん
8
図書館本。縄文もケルトも興味があるので読んでみたが、本を読んでいくと時代的には弥生とケルトもしくは縄文と先ケルトだよね?タイトルに違和感。地図や遺跡の平面図が欲しい。全体的にイギリスメインの内容かな。大陸の両端というかけ離れた地でありながらイギリスと日本の新石器時代にみられる共通点はホモ・サピエンスとしての共通認識によるものだということはわかった。ここは納得できるところ。ケルトのぐるぐると縄文のぐるぐる模様に関連があるのかと思わせるような並べ方だと思ったのに、直接的な関係がなくて残念。なんでこのタイトル?2017/07/15