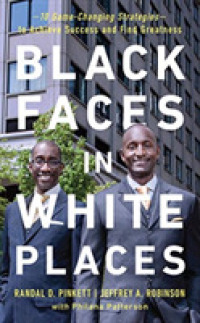内容説明
カントにニーチェ、キルケゴール、そしてサルトル。哲学書は我流で読んでも、じつは何もわからない。必要なのは正確に読み解く技術。“闘う哲学者”が主宰する「哲学塾」では、読みながら考え、考えつつ読む、〈哲学の作法〉が伝授される。手加減なき師匠の厳しくも愛に満ちた授業風景を完全再現。万人に開かれた哲学への道がここにある!
目次
はしがき
第一講 ロック『人間知性論』
第二講 カント『プロレゴメナ』
第三講 ベルクソン『意識に直接与えられたものについての試論』
第四講 ニーチェ『ツァラトゥストラ』
第五講 キルケゴール『死に至る病』
第六講 サルトル『存在と無』
原本あとがき
文庫版へのあとがき
解 説 入不二基義
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
テツ
21
中島先生の哲学塾カントにはたまに参加させて頂いていますが、良い年こいて生きるためには何の必要もない事が気になって気になって仕方がない社会不適合者が世界にはわりとたくさん存在するんだなあと確認すると何となく気が楽になる。哲学書を読むには知性やセンスも大切だけれどある程度のテクニックが必要であって、独学ではなかなか到達することの出来ない部分に気づかせてくれる授業形式は自分のようなアホにも新たな発見があります。考えること。根源的なことが頭からどうしても離れないのなら一度参加してみても良いかもしれません。2017/05/15
どらがあんこ
13
私なんかはなんやかんやでコンテクストに頼って外堀から埋めるようにして城を攻略した気でいるのだが、結局攻め込むことができていないのだ。本書では「自分なりに置き換えて」といった言葉が出てくるが、この翻訳作業は決して具体例に置き換えれば良いと言う訳ではない。内在しつつ、それを外側に打ち出してゆくという二重の立場から読む必要があるのではないだろうか。2019/03/09
チネモリ
6
本書にはロック、カント、ニーチェなどの様々な哲学書が登場する。哲学書を我流で読んでも分からないのは哲学には「作法」があるというよりも各々哲学者の思考形態、言いかえれば「流派」があるからだ。このことを「参加者」と共に追体験できた。2017/08/08
きゆう
5
自分の哲学の読み方が全然なっていない事が分かった。 哲学塾でのやりとりを読み進めながら一緒に考えて、分かったような感じから、全く分からない感じまで体験できた。あの分からない文章を理解する人がどう考えて読んでいるのかがイメージできただけでも良かった。 2018/07/07
伊崎武正
4
哲学書は我流で読んでも実はわからないということは、中島氏が数々の著書の中で再三にわたり述べてきたことである。だから哲学書を読むときは普通の読書とはやり方を変えねばな、と思い取り組んできた。それでもやはり理解が及ばないところだらけだ。本書の、複数名と中島氏との対話という形式は、正直すごく読みづらかった。氏の一般向けの本に、カントの書を噛み砕いたものがあったが、ああいう解説のみの本も十分わかりやすいので、これからどんどん出してほしいという思った。2019/07/24