内容説明
日常生活のさまざまな場面で体験する「痛み」。痛みは、生きていくうえでの防御機能のため、警告の役割もしています。私たちが受ける刺激は、皮膚下の侵害受容器を活性化させ、感覚神経を通って脊髄に伝わり、大脳で痛みとして認識されます。体内で起きている「痛み」のメカニズムを解説します。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
kaizen@名古屋de朝活読書会
20
#説明歌 痛覚のふしぎ体性感覚は痛温冷痒受容器分布 慢性痛記憶学習同仕組カルシウム依存性リン酸化酵素2017/09/09
テイネハイランド
17
図書館本。医学/薬学/看護学を専門で学んだ人以外には、意外と知らない痛覚のメカニズムについて解説した本。本の途中で痛覚とは無関係の感覚の解説があったり、使われている医学・解剖学上の用語に説明不足の点があったりするので、この本を読むだけだと若干消化不良気味。それでも、唐辛子の主成分カプサイシンに反応する受容体が温度センサーの役割をしていたり、炎症に伴う痛覚過敏反応についての詳しい説明が載っていたりと個別には興味深い箇所も多く書かれているので、神経についてもっと知りたいと思うきっかけにはなりました。2017/04/26
アルカリオン
7
多岐にわたる内容の、歯ごたえのある本。よい勉強になったが、一般向け書籍としてはやや読みにくいか。核心部分のみ要約すると、以下の通り。痛みは、損傷部位を安静に保つためのツール。痛みの原因が取り除かれない状態が続いているうちは、痛みの信号が脳に届き続ける。すると、反復学習と同様のメカニズムにより、痛みが「記憶」されてしまい、痛みの原因を取り除いても痛みが継続することになる。このように、慢性痛は不適切な記憶・学習に起因するものなので、認知行動療法により、負の痛みの記憶を消去することで治療効果が期待できる。2018/05/11
Happy Like a Honeybee
7
200年前まで、人類は麻酔なしの手術を行っていた。正座と末梢神経の関係。コカインの医学応用を発見したフロイト。カウザルギーの神経再生治療。 最先端の医療が受けられる、日本の保険制度を再考する契機に。2017/06/05
くまくま
4
痛みの感受性は遺伝により個人差があること。正岡子規の経験した脊椎カリエスの痛みは想像するだけで恐ろしい。無痛症なんて一見うらやましい先天性疾患の家系も存在するが、痛み=身体からの警告を受け取れないが故、早死にの傾向がある。2021/09/18
-

- 電子書籍
- ライブダンジョン!【分冊版】 9 ドラ…
-

- 電子書籍
- ウチの皇太子が危険です【タテヨミ】第8…
-
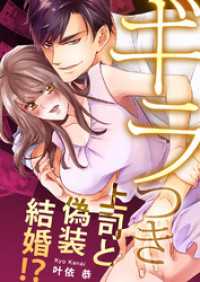
- 電子書籍
- ギラつき上司と偽装結婚!?【全年齢版・…
-
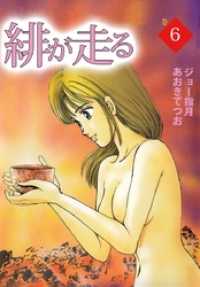
- 電子書籍
- 緋が走る(6) まんがフリーク
-
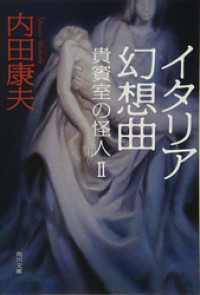
- 電子書籍
- 貴賓室の怪人2 イタリア幻想曲 角川文庫




