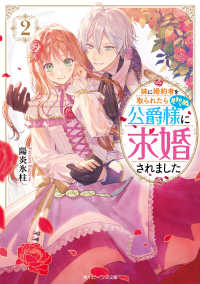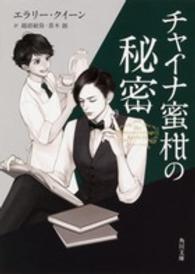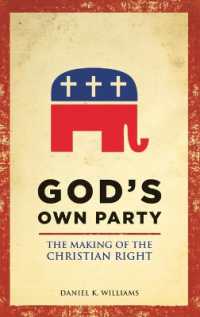内容説明
人々の目に触れることがない、精神科単科病院の「身体合併症病棟」。
ここがどのような場所で、どのような人が生き、そして死んでいくのか
精神医療は、一般にも医療の中でもタブー視されているのではないかと考えます。本書は、少しでも精神医療を知るきっかけにしてほしいと、日経メディカルOnlineで執筆したコラムをまとめました。
・なぜ、長期間退院できないのか。
・なぜ、精神科医が身体疾患を診るのか。
・なぜ、転院を断られるのか。
・なぜ、家族は治療を拒否するのか。
・なぜ、精神科病院は人里離れた場所や山の麓に多いのか。
精神科単科病院で亡くなっていった人たちの人生や、家族・友人との人間関係を通して、精神科疾患を有する人の日常や精神科医療の実際を描き出すと同時に、胃瘻造設や延命治療の是非、誤嚥性肺炎、患者家族への説明の難しさなど、終末期医療に共通する医師の悩みも吐露されています。
特別編として、相模原障害者施設殺傷事件についても書き下ろしています。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
瑪瑙(サードニックス)
52
読みやすかったです。でも、う~んと唸ってしまいました。精神科病院で長期入院してそこで亡くなる方々。その最期に寄り添うのは家族であったり、友人であったり、病院のスタッフだったり…。なぜ長期入院しなければならないのか?そこには『差別』が厳然と存在しています。現実として私は女なので警戒心が強いし、大声をだしたり、ブツブツ言いながら歩く人を見かけるとどうしても避けてしまいます。怖いと思ってしまいます。ごめんなさい。難しいです。2019/07/14
rokoroko
18
重い話をさらっと描いている。長期入院している患者を一人一人のエピソードが書かれていて今年[どんぐりの家」と言う漫画を読み障碍を持って生まれた人が精神病院に入ると言うエピソードがあり胸がつまった。ではどうやって生きれば良かったのか!と言われるとまたまた胸が痛い。2019/11/01
kanki
15
何年も入院し、ガンなどで亡くなる。告知の問題、治療の意思、家族の意向。ノメール法、0.3m以下は吐けない。2024/08/21
最後の羅針盤
8
学術的にも叙情的にも踏み込み過ぎることなく、あっけないほど正直な内容だった。正直さは強さ。その強さは著者の怒り。精神科病院で長く暮らして生涯を終えるしかない人生に当事者を追い込むのは、社会のスティグマ、それに痛めつけられた家族、そして精神科医療従事者自身が抱く諦念であることがやりきれない。経済優先で病床が削減されていく現在、寄り添う人のいない死が増えていくことは避けられないことなのだろうか。静かな怒りが広く共有されることを願う。2017/05/26
n75
6
精神科患者に纏わる本をいろいろ読んでいるが精神科単科病院の内情がかなり詳述されているのは珍しい。あくまでも医療者向けで、しかし一般の人にも読めるようにとかなり平易に書かれており、精神科患者に関するものに多いスキャンダラスな温度がほとんどなくむしろ淡々としている。相模原の事件についても少し触れられており、精神科医としての葛藤なども伺える良い本だった。医療者以外にも読んで欲しい。2017/11/06
-
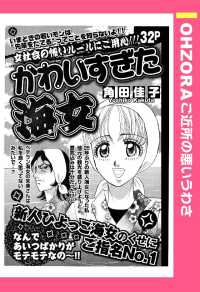
- 電子書籍
- かわいすぎた海女 【単話売】 - 本編…