- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
<本と日本史>は「本」のあり方から各時代の文化や社会の姿を考え、当時の世界観・価値観を究明する歴史シリーズである。本書が扱うのは、親鸞聖人の手紙や『平家物語』などの「声の記録」だ。その当時、文字を知らない大多数の民衆には「声」によって文化や思想が伝えられていた。親鸞聖人が遠隔地の弟子に向けて語りかけるように書いた情感溢れる手紙を読み解き、当時の知識人と民衆の関係性を鮮やかに描き出す。また、同時期に成立した『平家物語』にも触れ、「声」が「文字」として書き留められることで成立した中世文化の誕生の背景を解き明かす。日本中世史学の泰斗による研究の集大成となる一冊。【目次】まえがき――中世を体現する本/第一章 親鸞の著述/第二章 中世の手紙/第三章 世の移り行きを書く/第四章 平家の物語/あとがき――中世の声と文学/参考文献
目次
まえがき――中世を体現する本
第一章 親鸞の著述
第二章 中世の手紙
第三章 世の移り行きを書く
第四章 平家の物語
あとがき――中世の声と文学
参考文献
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
浅香山三郎
11
大隅さんの本は久しぶり。引用が多く、本シリーズは原文の鑑賞と解説に重きを置くのか、余り新味もないけれども、親鸞の書簡等、中世の仮名の手紙の味はひをたどだとしくも感じてみるにはよいか。『平家物語』も『愚管抄』も拾い読みでなく通読したいと思ふも、必要がないとしないだらうなと思ふ。2017/12/16
うえ
5
日本中世における記録、特に手紙に焦点をおいての考察。たとえば親鸞の娘、覚信尼の手紙は日本では珍しい幻視の記録。母と娘が越後と京都と離れて暮らしていたために信心を吐露した詳しい手紙の内容になったという。著者はヨーロッパ中世における女性詩人ハデウェイヒの『幻視』のことも挙げ、宗教体験を述べた多くの文書があったことに言及している(『女性の神秘家』)。覚信尼の手紙は1911年に西本願寺の宝物庫で発見。覚信尼の手紙は子の覚恵と孫覚如は書き込みをしているのだという。他に八木『パウロ・親鸞*イエス・禅』にも言及がある。2024/05/14
ikeikeikea
1
親鸞等の手紙と平家物語についての引用と解説から成り立っている本。前半の親鸞の手紙は親鸞自身が平易な言葉で自らの教えを解説してくれてとても有益であった。ただ後半の平家物語の章は平家物語の引用とちょっとした解説で成り立っているのであまり新規性がなかった。中世人の手紙だけで一冊書けば良かったように思う。2017/01/25
飯田一史
0
前振りでしている声の話があまりないのでは……2017/06/21
四不人
0
後段の『平家物語』や軍記物のとこは、やや薄味か。書物は歴史を叙述することから始まった、というのは本書にもある表現だが、本書を読んで思ったのは、日本では一部の「本」は、手紙を束ねたものから始まってる、ということ。そう言えば、「庭訓往来」だってそうだもんな。2017/04/22
-

- 電子書籍
- 悪役令嬢に幸あれ! ~悲運な悪女が幸せ…
-
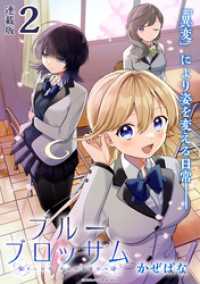
- 電子書籍
- ブルーブロッサム 連載版:2 ブシロー…
-
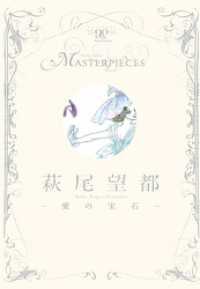
- 電子書籍
- 萩尾望都-愛の宝石- フラワーコミックス
-
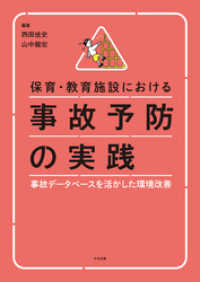
- 電子書籍
- 保育・教育施設における事故予防の実践 …





