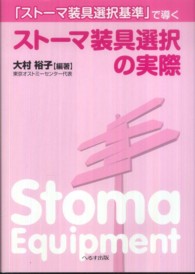内容説明
昏迷・妄想・幻聴・視覚変容……これらの症状は何に由来するのか。病名の誕生当初から「人格の崩壊」「知情意の分裂」などと理解されてきた謬見が次第に正されつつある。患者はどうして、どんな不具合を抱えているのか。精神科臨床に長年携わってきた著者が、脳研究の成果も参照し、治療につながる病気の本態と人間の奥底に蠢く「原基的なもの」を語る。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
どらがあんこ
9
読むという行為と考えることの位置づけに惹きつけられた。取り囲むものとしてでなく予測のコンテクストで読むとそれは再表現される。だから閉じ込められるものでもないのだろうなと。2019/03/03
またの名
5
分裂病の患者は他人の目を見ないなどと言われてたが医者の方が何か書きながらカルテばかり見てるのではと思った物理学者ファインマンを、引用して同調する風変わりな精神科医の講義(自閉症圏でも視線の話が同様)。やはり分裂病が放つとされる様子を示す概念〈ただならぬ気配〉にも「ただならぬ気配をお前(治療者)が感じているだけだろうが」とツッコみ、独自の切り込みで理性の限界を画す病を論じていく。脱施設化と自我心理学の流れを著者は自認。古今の理論を沢山参照してるものの、学術文庫というより講談と呼ぶ方がまさにピッタリ来る話芸。2023/10/02
雑食奈津子
5
統合失調症について学べるのかと思いきや、著者が行った公演の文字起こし。興味深く読めたが、統合失調症について基本的なところは分からず。2019/04/29
qbmnk
2
同時進行で木田元と著者の対談「精神の哲学・肉体の哲学」を読んでおり、相補的なところもあって面白かった。この本は精神医学者である著者の臨床での豊富な観察と脳科学から哲学に及ぶ幅広い理論的な考察があり、ひとつの病気としての統合失調症について理解の助けになった。ふつうのことができないとはどのような状態なのか、患者が何に困っているのか、どうすればふつうのことができるようになるのかという視点で統合失調症患者に対応していった経験が語られている。最終講義の講義録で口語なのも読みやすい。2018/09/12
amanon
2
以前単行本で読了したものを文庫版にて再読。最初読んだときは心地よかったべらんめえ口調が今回はちょっとくどく感じたな(笑)。それはともかくとして、理屈より臨床ありきという著者のスタンスには改めて好感を抱いた。また、分裂症から失調症へと呼び名が変わったことにある程度の意義を認めながらも、あえて分裂症という言葉を使うところに著者ならではの拘りを感じる。それとかつて一部で持て囃された、分裂症を神聖視するような思的潮流への苦言にも考えさせられるものがあった。そして、やはり現状がなかなか変わらないという事実が重い。2017/07/08
-

- 電子書籍
- 異世界から聖女が来るようなので、邪魔者…
-

- 電子書籍
- HONKOWA 2023年7月号 HO…
-
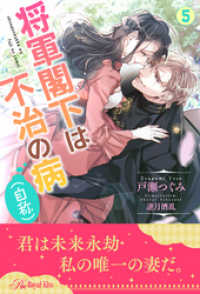
- 電子書籍
- 将軍閣下は不治の病(自称)【5】 ロイ…
-

- 電子書籍
- 明治維新 1858-1881 講談社現…