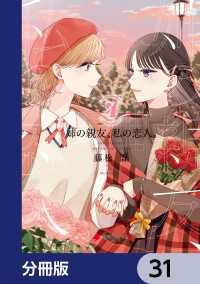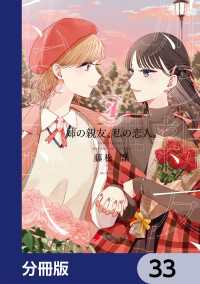内容説明
福井県・水月湖に堆積する「年縞」。何万年も前の出来事を年輪のように1年刻みで記録した地層で、現在、年代測定の世界標準となっている。その年縞が明らかにしたのが、現代の温暖化を遥かにしのぐ「激変する気候」だった。人類は誕生から20万年、そのほとんどを現代とはまるで似ていない、気候激変の時代を生き延びてきたのだった。過去の詳細な記録から気候変動のメカニズムに迫り、人類史のスケールで現代を見つめ直します。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
KAZOO
144
以前ラジオ深夜便で聞いたことがあり気になっていましたが、この本を読むとさらに興味がわきました。三方五湖の一つの湖が気候変動を知るための世界標準になっているということは驚きでした。1年で0.7ミリづつ花粉などが堆積されていくらしいのですが、そのままだと結局最後は地上に出てしまうらしいのですが地盤の関係で1年に1ミリづつ沈むのでちょうどいいらしいのです。知的好奇心を満足させてくれました。2017/06/07
absinthe
117
10万年前の気候をどうやって再現していくか。慎重にデータを積み重ね推理する。この解き明かしていく過程の面白さ。素性のよいデータは実はまれにしか存在しない。水月湖の存在は重要だった。語り口も面白いし、研究者の本音や苦労も垣間見れる。良本。2018/03/30
どんぐり
84
メッカの巡礼で1300人超死亡。気温50度を超え猛暑を経験したことはないけれど、ここ数年の気候変動に、地球は大丈夫かと思って読んだ。「地球の健康」×「人間の健康」=プラネタリーヘルスは課題だが、結論は、「数十万のスケールで見た場合、「正常」な状態とは氷期のことであり、現代のような温暖な時代は、氷期と氷期の間に挟まっている例外的な時代に過ぎない」ということだった。昨日まで続いたことが今後も続くだろうという人間の思考(人間のスケール)を戒めるように、地球のスケールから古気候学が解き明かしてくれる。→2024/06/30
ホークス
84
面白い科学書には、良くできたミステリーの味わいがある。謎があり、スリリングな展開があり、意外な真実にたどり着く快感がある。本書は何万年も前の気候を再現し、当時の祖先の暮らしに光を当てる。その手法が意外であり、しかも日本の湖が舞台である事に驚く。氷期(氷河期)と間氷期の原理と現在がどの時期なのか、そしてどこまで将来予測が可能かが示される。話はさらに、現在言われている温暖化をどう考えるか、寒冷期に農業が発達しなかった真の理由に及ぶ。「科学の問題」と「哲学の問題」をキチンと分ける姿勢も信頼できる。2017/05/10
syaori
76
古気候学の本。作者は放射性炭素年代測定の誤差較正のための国際的な「ものさし」IntCalに採用された水月湖のデータ整備に携わった人物で、その過程に絡めて古気候学とは何かを示します。そうした後でそのデータから過去15万年の湖周辺の気候を再現する様子は鮮やかで胸が躍るよう。しかしそれを含めた研究から見えてくるのは、地球は激しい気候変動を繰り返していて、人類の活動の影響がなくても将来必ず気候は再び「暴れ始める」ということ。その時代を生きるために多様性を活かせる社会を作ることと語る作者の言葉が胸に強く残りました。2021/11/08