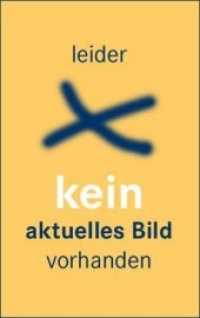内容説明
ビッグデータ時代の到来、第三次AI(人工知能)ブームとディープラーニングの登場、さらに進化したAIが2045年に人間の知性を凌駕するというシンギュラリティ予測……。人間とAIはこれからどこへ向かっていくのか。本書は基礎情報学にもとづいて現在の動向と論点を明快に整理し分析。技術万能主義に警鐘を鳴らし、知識増幅と集合知を駆使することによって拓かれる未来の可能性を提示する。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Kawai Hideki
75
第二次人工知能ブームとその後の冬の時代を経験した研究者による、第三次人工知能ブームの解説と、行き過ぎた仮説への警鐘。レイ・カーツワイルのシンギュラリティ仮説に真っ向から反論。ただ、第三次ブームに対する苦々しい気持ちが先行しすぎたのか、批判がやや感情的で散漫になっている気がする(特に第三~四章)。一方、最終章の、ビッグデータ、人工知能、集合知を三位一体で活用した「知能増幅(IA:Intelligent Amplifier)」と、人工知能の社会的影響を考えるための情報教育のあるべき姿は、着地点として良かった。2016/09/14
saga
50
副題を意識しないままに読みはじめた。人工知能を完成させるためのビッグデータ……そんな誤解があった。しかし、本書を読み進めるうちに、人工知能に対する誤解や、SFに出てくる「意思」を持った機械、人類に君臨するコンピュータが出現することの困難さを理解できた。p.147「そういう疑問をふまえて、近未来のコンピュータ文明のあり方をさぐるのが本書の目的」が腑に落ちるのだ。基礎情報学をもっと知りたい。2023/11/18
かごむし
40
手に取ったきっかけはたまたまだったけれど、2045年に到来するとうわさされるシンギュラリティ予測に恐れおののいていたところだったので、非常にタイムリーな読書になった。正しい知識を持つことは、物事を判断する上での基本で、ここをおろそかにしては、マスコミや、風潮に踊らされてしまうなあなんてことを思った。著者はコンピューター工学研究者から、情報社会や情報文化を論じる学者に転身した経緯を持つ。そのため、現場のこともわかり、それが意味することも理論的に論じられるという稀有な論文になっていると思う。非常に面白かった。2016/08/10
おさむ
37
「人間より賢い人工知能が我々から仕事を奪い、世界を支配する」こんな暗〜い未来予想は見当外れと明言する著者は、この分野の第一人者だけに説得力があります。個人的にはスピルバーグ監督の映画のイメージが強いAIですが、AIによって変わるのは「仕事の質」だけなんだそうです。実用にあたっては技術だけでなく、社会や人間性の観点からの検討が大切という指摘はうなづけます。日本人のAIやロボットに対する見識はノー天気で幼稚すぎるとバッサリ。やはりアトムやドラえもんの影響が大きいんでしょうかねえ笑笑。2017/07/04
ころこ
34
AIによる可能性と限界を論じています。数日前に孫正義が「AIの限界論ばかりはびこっていてけしからん」と、やる前から否定的な反応をする日本人の保守性を嘆いていましたが、本書はその批判に当たりそうな本です。著者は現在のAIについて「全件処理」「質より量」「因果から相関へ」といったビックデータの特徴を一つ一つ検討した上で、認識技術のブレイクスルーではあるが単にそれだけと断じています。フレーム問題も記号接地問題も、要するに曖昧に処理する人間の特徴を機械が上手く処理することが出来ないためと、「AIに出来ないことは何2021/04/01
-

- 電子書籍
- リスクはじきに目を覚ます―――内部統制…
-
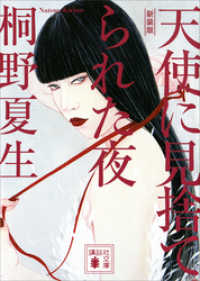
- 電子書籍
- 新装版 天使に見捨てられた夜 講談社文庫