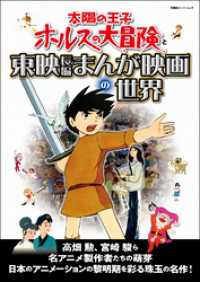- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
大水の出る場所は、決まっている! 地名研究半世紀の成果がここに! 災害大国・日本でもことさら多いのが水害。この四半世紀で1300件以上発生し、死者・行方不明者は1700名近くにのぼる。なぜ、これほどまでに多いのか? 自然の宿命もさることながら、水の出やすい旧城下町に人口が集中していることも大きく、人災である側面も否めないのだ。繰り返される水害を防ぐべく、古(いにしえ)より人は地名に思いをこめて警鐘を鳴らしてきた。かつては海であり、沼沢(しょうたく)や砂地、川があった場所、何度も土地が崩れた地点には、必ず鍵となる語が地名に残されている。例えば、崎、龍、瀬、狛、駒――の字が警告するものは何か? この日本で危ない場所は、すでに決まっている!
目次
◎古記録が記す関東北部の沼沢群 ◎カイト地名の実態は? 水街道とは? ◎決壊地点の対岸にあった「押切」という地名 ◎龍ヶ崎市の「龍」は何を意味するか ◎千間堀がいつの間にか「せんげん台」に ◎オゴセ(越生)とは「驕る瀬」のことか ◎日本の地名は、ほとんどが災害に関連する ◎目黒川は「メグル(曲流)川」 ◎継体天皇はなぜ樟葉宮で即位したか ◎六甲山地と灘が危ない ◎地名の「御影」は「水・欠け」のことか ◎なぜ「坂の町」長崎に、県庁が置かれたのか ◎「緑の丘」の中腹は危険きわまる◎大字「八木」とは、どんな地名か?……
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
naginoha
48
野暮用にて地名を調べる必要が生じ図書館から借りた。 金達寿氏は日本の地名をことごとく朝鮮由来とした説を流布して有名で、この作者も批判しているが、この楠原さんはあまりにも水害にとらわれすぎに感じた。 2020/09/29
鈴
39
こんな時期だからこそ気になったタイトルだが、『長崎大水害』を目当てに読んだ。…たまたま今日は長崎大水害の日だった。2018/07/23
くまくま
4
地名の漢字は基本あて字だとそうだ。当てられた漢字に隠された意味、古の人々が残した災害の跡が見える。内容は興味深いが、ところどころ筆者の中央政府、地方公共団体による都市開発、土地開発に対する怒りが見られ、読んでいて少し引っかかる。2019/08/26
瓜月(武部伸一)
3
2015年秋、僕が関係するNPOの所在地、東武伊勢崎線せんげん台駅一帯が水没する豪雨があった。実はせんげん台の名称は、駅近くを流れている千間堀(新方川)に因んでいるという。江戸初期、古利根川、元荒川、古墨田川に囲まれた低湿地だったこの地域が水田化された際、開削された農業排水路が千間堀。今のせんげん台駅周辺は元々、周辺の雨水が集中する地形なのだろう。では「堀」がなぜ丘を意味する「台」に変わったのか。せんげん台駅の開設は1967年、宅地開発ブームの時代。容易に理由が推測できる。このような事例が多く書かれた本。2018/11/10
kira
2
ほうほうと頷ける説もあれば、ちょっと飛躍しすぎてたり、穿った見方で論じている地名の考察もあるので、ちょっと注意が必要かもしれない。しかし、地名の「おと」を重要視しているのはいいと思う。漢字は当て字なのでね。興味深く読めました。2016/08/26