- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
「旅する学者、そして詩人」管啓次郎(読売文学賞)と「カルト的人気漫画家」小池桂一。異色のタッグが描き出す、神聖なる大地で生きる人々の豊穣な世界観。 私たち人間が、この地球の上で生きていくとはどういうことか?
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
よこしま
29
父なる太陽。母なる大地。◆「中学生からの大学講座」シリーズで執筆された管さんのインディアンの魅力をもう少し掘り下げて、読んでみました。◆発達しすぎて飽和状態な“資本主義”に対し、中学生の時から疑問を持っていましたが、行き着いたところがインディアンだったとは。◆この世界まででなくても、同シリーズのオーラスで西谷さんが農業に戻るべきと述べていた旨、著書の内容からは離れますが遠からずかなと。◆自然に対し敬い、動植物らと共生する彼らの哲学は見習う箇所は多いです。◆“生きる”と“儲ける”とでは大きく違います。2015/05/13
mitei
23
マンガで神話の部分の大半がよく分かった。日本の神話も太陽が密接に関わっているし、太陽というのは重要なものだということが分かる。2011/07/19
たくのみ
11
「インディアン嘘つかない」で育った世代としては、やっぱりアメリカインディアンなのだ。侵略の事実を忘れないための名称の復活。ジャクソンの裏切りをはじめとする、インディアン迫害の歴史、そして、バッファロー女、ハクトウワシ、太陽と月、豊かな神話と文化。勇敢なナバホ族の創世神話がスゴイ。西洋文明の侵略も、彼らの歴史の一コマ(マンガでは2コマ)でしかないのだ。2016/06/02
スミス市松
10
この著者の最良の書とは言い難い。繰り返し述べられる現代物質社会との二項対立に些か辟易もすれば、内容はアメリカ・インディアンの各エピソードを交えつつ彼らに広く認識される自然観の紹介にとどまっており、取り上げられる部族も恣意的で、移住型(ナバホ、アパッチ)や定住型(プエブロ系)の差異などといった概論的知見を得ることはできない。むしろ彼が書こうとしたのは「土地の倫理」であり、土着の人々がどのようにしてその場所に応えてきたか、そして彼らの生き方を外部の人間がいかに哲学として学び取ることができるかということである。2018/08/28
ハチアカデミー
9
C アメリカ・インディアンの自然観の諸相と、その奥深さを考察した書。「土地」を機軸に、現代の日本人が失った自然への敬意や、自然の中で生きるという感覚を呼びもどさんとの試み。が、あまりにも二項対立すぎて、アメリカン・インディアンの各部族による差異や、逆に西洋化されている文明国の差異が見えてこない。それでも、タイトル通り、野生の中にいきる人々の哲学を知る手引きとしては良書か。後半に挿入された小池氏の漫画もビジュアルに神話を読むことができ楽しめはするが、一冊にまとめる意義は感じなかった。たぶん版元の意向だろう。2012/08/15
-

- 和書
- 山猫座 - 句集
-
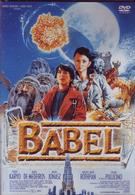
- DVD
- バベル 失われた地図と魔法の水晶







