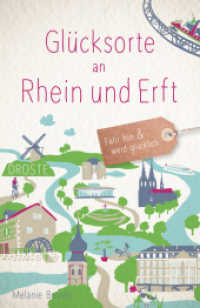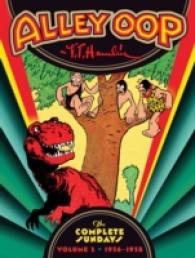内容説明
伊豆半島衝突、富士山噴火、海に沈んだ東京・大阪・京都、消えた縄文文化、移動する琵琶湖、瀬戸内海をナウマンゾウが闊歩する──。1500万年前、ユーラシア大陸の東の端から分かれて生まれた日本列島。現在、私たちが目にする風景・地形も、時代をさかのぼると全く違った顔を表します。本書ではおもに100万年前以降を中心に、複雑な地形に富んだ列島の成り立ちを解き明かします。驚きに満ちた日本列島史!
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
やすらぎ
206
山があり海がある。川があり谷や平野ができる。地球が生きている限り、特にプレート付近で地震や噴火は繰り返されてしまう。そのなかで、私たちはどう生活していくのかを冷静に考えたく、改めて日本列島の成り立ちを学ぶために本書を手にする。気を静めるために。地形はどう形成されたのか、大地に刻まれた事実を地域ごとに解説している。近畿三角帯は興味深く拝読。中国四国地方の複雑な地形は、大地の動く方向でつくられたもの。知れば知るほど、この列島は動き続けていることがわかる。人類の力では対応できないこともある。備えておくしかない。2024/01/04
あすなろ@no book, no life.
97
日本列島はどの様にして形作られたか?それは氷期等の外的営力とプレート運動の内的営力によるものである。我々が今見ている地形は、絶えず地形変化がある何万年もの時の中で、ただスナップショットを見ているに過ぎず。こんなことを俯瞰的に理解出来る本。後半は地方別検証になっている。例えば古富士や新富士の話。その他、日本でのポンペイ大噴火の様な南九州の7300年前の火砕流噴出等盛り沢山。様々な土地を出張で訪問し、土地や土質を考える事がある僕には知的好奇心以外にも雑学的な勉強が出来たのであった。2020/05/02
ひろき@巨人の肩
78
1500万年前にユーラシア大陸から分かれた日本列島。東北日本と西南日本が日本海の開裂と伊豆バーの衝突を得て、100万年前に現在の弓状の形をなす。それ以降の各地の100万年史を紹介する本書。今後、日本旅行を楽しむために手放せない一冊。北海道は大雪山、石狩平野、石狩川。東北は三内丸山遺跡、応羽山脈、三陸リアス式海岸。関東は関東平野、武蔵野台地、東京低地、箱根火山、御殿場泥流、足柄平野。中部は富士山と日本アルプス。近畿は近畿三角帯、神戸の兵庫県南部地震。中国・四国は南海トラフ、瀬戸内海。九州は九州シラス台地。 2025/01/18
さつき
68
日本列島がどのように現在の形になったかが地域ごとにまとめられています。南北に細長い列島はその成り立ちも一様ではないんですね。知らないことばかりで刺激的な読書でした。特に地震による隆起や活断層の定義の話し、自分の住んでいる関東についての記述が興味深かったです。大地は長い時間をかけて動き続けていて、今のこの風景が永遠に続くわけではないことに、当たり前ですが気付かされました。2017/09/24
十川×三(とがわばつぞう)
61
面白い。火山、地震、岩質、気候変動など幅広い。▼10万年毎に氷期が訪れる。8万2023年には、海退で海が120m下がり、東京湾は再び陸になるかも。ツバル諸島も復活。ただし8万年後、人類がどうなっているかは想像もつかない…。▼伊豆半島は100万年前からの新参者。▼独ナウマン博士がナウマンゾウ、フォッサマグナを名付けた。2023/08/22