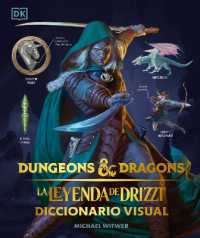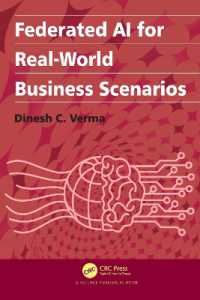内容説明
応仁の乱よりも50年ほど早く戦国時代に突入した東国を舞台に、単なる戦国通史としてだけではなく、戦乱を中世の「戦争」としてとらえ、「軍事」の視点で戦国武将たちの実情に迫る一冊。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
roatsu
20
中部以西に劣らぬ激動を繰り返した戦国期関東の百数十年の変遷に対する著者の合理的で興味深い洞察が冴えている。表紙に三つ鱗が際立つのは著者の後北条氏への評価ゆえだろうが、実際に宗瑞からの歴代当主が成した事績は凄いの一語に尽きる。諸将が対峙した人間のどす黒い本質に発した現実とその対応に要した冷酷な合理精神を現代日本人は国際情勢を踏まえて真剣に再認識すべきでは。関東地方で起きた諸勢力の興隆と衰亡物語としてだけでなく、現代流の主観的で甘い英雄願望など入る余地のない戦国時代の容赦ない営みを知る上でも好適な一冊。2016/04/10
YONDA
18
西股さんの本は、学研から発売された三冊に衝撃を受け、通説をぶった切る西股節に感心することが多かった。今回は前三冊よりもおとなしくはあるが、所々に西股節が炸裂し、大変面白かった。中でも、「長尾景春と太田道灌」の項は、信長・信玄・謙信達が出てきた時代のちょっと前の事なので、「名前は知っているけど何した人?」ぐらいの知識なので非常に勉強になりました。また、信玄が三国同盟を破棄した頃からの戦略的迷走、北条家の小田原征伐に対しての戦術なども興味深い。西股さんの文は私の体質に非常に合っているみたいです。2015/11/16
jiangkou
12
装丁とタイトルから固い、文も読みにくいものかと思ったら、しょっぱなからナウシカのセリフが引用されていたり、全体的に読みやすかった。内容は北条、武田、上杉を中心とした東国戦国大名の戦史をつぶさに書いたなかなか無い本。特に関東管領について理解が深まった。北条の描写が細かく100年も持つ帝国を作った政治機構、小田原攻防は劣勢ではあったが勝ち目を探って戦略を練った戦役だったなど深かった。上杉、武田の描写も読みやすかった。同じ作者で北陸、近江も読みたい。想定外のよい本。2018/03/27
kawasaki
11
『戦国の軍隊』が面白かった作者による戦国関東百年史。『歴史群像』誌発表作で、ご自身「現代版の軍記物」とは述べておられるが、学問的な研究動向にきちんと足の着いた安心感がある。それとともに、確定できない部分を埋める「観てきたような確からしさの面白さ」があって、ちょうどよい塩梅。長尾景春、伊勢宗瑞、北条氏綱、武田信虎、長尾為景をはじめとする人々が、魅力たっぷりに描かれる。2018/09/08
スプリント
10
坂東武者たちの勢力争いと新興勢力である後北条氏の勃興。 鎌倉以前からの名家も多数登場するので読んでいて楽しい。2024/01/05
-
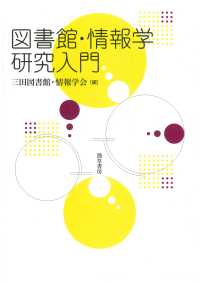
- 電子書籍
- 図書館・情報学研究入門
-
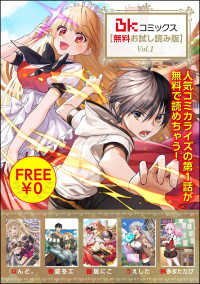
- 電子書籍
- BKコミックス【無料お試し読み版】 V…