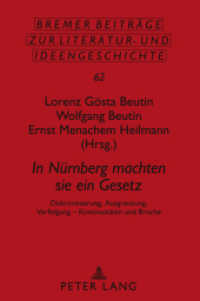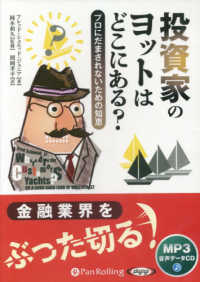- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
クラシックファンならずとも、モーツァルトの全作品にはK.**とかKV**などという番号が振られており、それをケッヘル番号と称することはご存じでしょう(たとえば交響曲第41番『ジュピター』はK.551)。誰から頼まれたわけでもないのに一作曲家の作品を調べ上げて分類し、番号を振る──。考えてみれば酔狂なことです。ケッヘルとはいったいどのような人物であり、どうしてこんな作業にとりかかったのでしょうか?
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
trazom
97
今年9月にケッヘル目録が60年ぶりに改訂された(627以降の番号はショック!)のを機に、積読だったこの本を読む。ケッヘルの真摯な姿勢に心打たれ、そんなケッヘルの生涯と業績を描く著者の温かな視線に深く感動する。いい本だ。何よりの驚きは、A.アインシュタインがケッヘルを軽蔑していたという事実。私は、ケッヘル・アインシュタイン番号の二重番号制はケッヘルへの敬意だと思い込んでいただけに、ケッヘルやヤーンに対する「おまえらは単なるディレッタント、俺は専門家」というアインシュタインの態度に複雑な思いを禁じ得ない。2024/10/19
luna
3
ケッヘルの話、というよりは、時代やウィーンなどの話。内容はともかく、かなり主観的な表現が多いし、全般的に文章がこなれていないのが気になった。妙に若い表現とかあったり。著者の年齢を見てうなった。同い年じゃん……2011/06/23
エピクト
3
モーツァルト作品番号に【のみ】名を残すケッヘルの評伝。当時たいへんな知識人だったケッヘルが何故モーツァルトの作品目録でしか記憶されないのか。それはメッテルニヒ体制下のビーダーマイヤーのディレッタントだから。それはともかく、作品目録の作成方法が、鉱物のコレクション分類を応用した、自然科学者的発想で行われていたと言うあたりが非常に面白かった。こないだ読んだ「モーツァルトの台本作者」もそうだけど「天才の周辺のみに名を残す【凡庸な知識人】の生涯」もなかなかに面白い(モーツァルト自身にあまり興味が無いんだけど)。2011/03/31
muneota
2
モーツァルトの作品といつも一緒にいるK:ケッヘルさん、名前だけはなじみのあった人物のひととなりを、この評伝を通して初めて知ることができました。メッテルニヒ体制の厳しい抑圧下で、生業とは別に学問・趣味に情熱を傾けた中産階級のディレッタント達、そんな一人の「凡庸」な人物の努力によって、モーツァルトの作品目録・最初の全集は散逸をまぬかれ世に出たのでした。例え名は残らずとも「凡庸な素人」でも何事かをなすことができた、幸せな時代だったのかもしれません。著者の小宮さんの卓抜な構成力に感心。頭の良い人だと思いました。2011/09/30
千葉さとし
2
ベートーヴェンを中心に据えたドイツ音楽を高める音楽史観への批判は多々ある、ではオーストリア、ウィーンとモーツァルトを中心にした音楽観はどのように形成された?その問いに、モーツァルトの作品番号で今も知られるケッヘルの生涯を通じて答える一冊かと。なるほど、普墺戦争にハプスブルク帝国の衰退、ふむふむ。なかなか説得的でした。また、ケッヘルがモーツァルト作品を整理した際の方法論はオープン・データベースとも言えそうで、なかなか射程の長い作りだったのだなと感心。ディレッタント万歳!(笑)2011/08/07
-

- 和書
- 黒沢明のいる風景