内容説明
十九世紀末、フロイトによって確立された精神分析学。彼の高弟ユングは後に袂を分かち、一派をなす――。人間存在の深層を探究した彼らの存在は、今なお我々に多大な影響を与え続けている。彼らは何を追い求め、何を明らかにしたのか。二人の巨人の思想の全容と生涯を、それぞれの孫弟子にあたり日本を代表する第一人者が語りつくした記念碑的対談。
目次
対話者まえがき 小此木啓吾
第一章 出会い
第二章 人間フロイト、人間ユング
第三章 人間の心をめぐって
第四章 夢を語る
第五章 文化と社会
関連人物解説
対話者あとがき 河合隼雄
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
獺祭魚の食客@鯨鯢
68
フロイト、ユング、アドラーらは無意識が人間の行動に様々な影響を与えることについて「哲学」しました。 神を否定したのが個人主義(自由思想)が近代合理主義の始まりでした「考える葦」も災厄の前にはとても弱い存在。 「今、ここ」でしか生きられない動物たちの方が逆に幸せな場合もあります。 どんな不幸があろうとも、その理由をしっかり考え「認識」するだけで不安感は少なくなります。 個々人がそれぞれと神(大いなるもの)と真摯に向き合うことで心の平穏を得られるなら宗教でも哲学でも構わないはずです。 2020/05/06
夜間飛行
67
老年まで母性に縛られたフロイトが女性に対して禁欲的だったのに比べ、母性とアニマ性を併せ持つ母に育てられたユングは、生涯女性の援助を求め続けた。また、無意識は文化の違いに影響されないと考えたフロイトに対し、ユダヤとゲルマンの無意識は異なると発言したユングはナチスへの協力を疑われてしまう。二人の違いが色々見えてきた所で、間にメラニー・クラインを介して両者がもう一度繋がってくるのに驚かされた。その辺はかなり高度な議論だが、何となくイメージとしてわかるような気もする。厳密になりすぎない対談ならではの良さを感じた。2014/06/15
ころこ
46
40年以上前の、かなり緩い対談集です。フロイトとユング両者の理論を比較するのはもちろん、性格や研究方法、対人関係などを比較しています。現在ならば評伝として実証的かつ抑制的に叙述することしか許されませんが、本書のようなざっくりとした感じが一般の読者には助かります。現在の風潮は、誤解が生じることを理由に理解を阻んでいるところがあります。冒頭で小此木が精神分析と地続きに語っているのは哲学と宗教です。最終章が文化と社会であるように、無意識を文化論として考えることは、今なお社会を意識する良いきっかけとなっています。2021/10/03
Hiroh
32
やっぱりフロイト、ペニスにこだわり過ぎよねえ。なぜペニスのない女に男が惚れられるのか、そうか!おんなにもペニスがあると錯覚するんだ!!…… フロイトに精神分析を受けると金持ちになり、ユングに受けるとアーティスティックになる。ユングは患者が社会にどう適応していくかということには関心が薄かった。日本では母性的な許しによって相手に罪悪感を与え、周りが自動的に言うことを聞くようになっていく。2024/05/05
ばんだねいっぺい
28
フロイトとユング。フロイトの横にユングを置き、ユングの横にフロイトを置けば、それぞれがよくわかるんじゃないかということを対話形式で行っている。母性社会の中では、男らしさは、それに奉仕した形となっているのではないかに衝撃を受けた。2025/04/26
-

- 電子書籍
- NHK 連続テレビ小説 おむすび シナ…
-

- 電子書籍
- 魔術学院を首席で卒業した俺が冒険者を始…
-
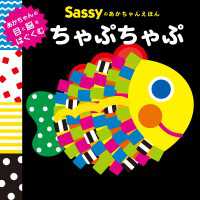
- 電子書籍
- Sassyのあかちゃんえほん ちゃぷち…
-
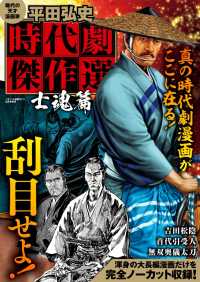
- 電子書籍
- 平田弘史 時代劇傑作選 士魂篇
-
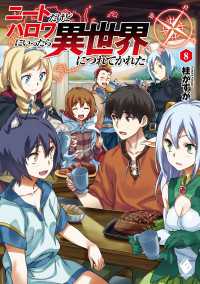
- 電子書籍
- ニートだけどハロワにいったら異世界につ…




