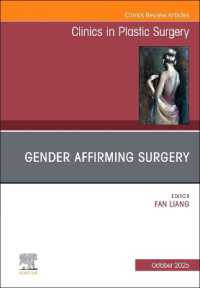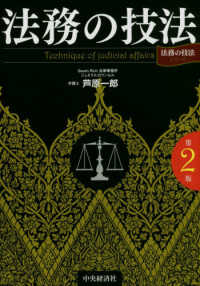- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
日中関係に付きまとうもどかしさ。それは、「経済関係が良好でも、どこかで「政治」が邪魔をする」一方、「政治的な関係が悪化しても、「経済」のつながりはなくならない」ところにある。この構図は最近になってはじまったわけではなく、近代以降の両国の交渉において何度となく繰り返されてきたのである。日本(人)は中国(人)をどのように理解し、付き合ってきたのか。経済関係を軸に政治・社会状況の考察を織り交ぜながら、一筋縄ではいかない両国関係の本質を解き明かす。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
えちぜんや よーた
85
沿岸部の主要都市を占領しても石油や鉄鉱石の重要資源を獲得できなかった日中戦争で、日本軍は中国からなぜ撤兵できなかったのか?この本を読むまでは「戦争で命を落とした10万の英霊に相済まない」という国民感情と陸軍上層部の見栄が原因だと思っていた。だがこの本によるとインフレーションを中国に転化するような通貨政策(預け合)をとっていたことも一因であることが分かった。このスキームから仮に現地軍が内地に撤退してしまうと、おそらく日本国内で猛烈なインフレーションが発生して、太平洋戦争とは別の悲劇が起こっていたと思う。2019/06/30
Hatann
5
労使間の対立がナショナリズムに結びつきやすい、中国政府の実力を軽視して対応を誤りやすいなどのことが指摘されている。ただ、ナショナリズムという言い方だと少しマイルドすぎ、端的に反日感情と言い換えてよいのでは。問題は反日感情を受けるだけのことをやってきたのかということ。個人の心情としては二分論に傾くが、この本では国民の多くが軍部の行動に賛意を示したことが仄めかされており、実際のところどうだったのか気になる。必要以上に卑屈になる必要はなく、何事も未来志向で議論すればよいが、認識しておいた方がよいものもあろう。2018/09/06
さとうしん
5
似たようなコンセプトの本は岡本隆司先生のものなどいくつか存在するが、本書では特に日中間の経済的な結びつきに注目。労使間の対立がナショナリズムに結びつく点や、日本側が中国政府の実力を軽視して対応を誤るといった現象が戦前から見られることを指摘。よく話題に上げられる中国のGDP統計に対する疑念についても、地道な研究によって代替的な推計がはじき出されており、実際の数字との誤差がどこから生じるかという問題についてもおおよそのコンセンサスが形成されているというが、その部分をもう少し詳しく説明して欲しかった。2016/12/10
in medio tutissimus ibis.
3
戦前の労使問題の根底にはナショナリズムのほかにも中国独自の労働環境への理解が足らなかったことがあったので、それを踏まえ日本企業は長い目で見て中国人労働者を大事にしましょう。正気か。意識が違うから問題になったという前提から、どうして自分たちの意識を押し出すべきなんて結論に至れるんだ?2018/06/17
うまのすけ
2
一九二〇年代の「五・三〇事件」から現在の「一帯一路」戦略まで、丁寧に整理された日中経済関係史。非常に長い期間を対象とする研究だが、全篇にわたって「日中はどうすればうまくお互いの利益を尊重しあいながら付き合うことができるのか」というテーマが貫かれている。蒋介石政権の「幣制改革」をめぐって日本で展開された「支那統一化論争」に関する分析が面白い。今の日本でも広く流布する「中国=異物」論の源流のようだ。また獅子文六の小説を通じて戦前の中国バブルを描くなど、挿話も豊富である。2017/08/17