内容説明
クロード・シャノンが記念碑的論文「通信の数学的理論」を発表したのは1948年のことだった。それから60余年──今では情報理論は情報通信のみならず、生命科学や脳科学、社会科学など幅広い分野に応用されるようになっている。情報理論は高度な数学を用いているが、“大数の法則”をおさえることでその本質がすっきりと見えてくる。シャノンのアイディアから情報幾何学の基礎までを、初学者にもわかるよう明快に解説、情報理論の考え方と仕組みを直観的に理解するための、第一人者の手による入門書。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
roughfractus02
4
不確実な知識を確実にするというシャノンの情報定義から始めて、確率現象としての情報と確率の関数としての情報量から概説する本書は、その手順として離散的通信(デジタル)から連続的通信(アナログ)へと進むが、そこには通信空間をリーマン幾何学の位相空間に設定して多次元間の写像によってその状況を記述しつつアナログ通信から通信理論を明確にしていく著者の意図がある。そのシンプルさへの意志は、高精度の測定での情報とエネルギーや換算関係での熱力学と情報のエントロピーの不均衡を状況ごとに区別する冒頭からも窺える(70年初版)。2017/12/07
Hiroyuki
3
前半はシャノンの論文の流れに沿った解説で、原著でわかりにくかったところが見事に補足されていて非常に理解が深まった。また、終章の退化写像理論はこれまでに勉強していないことで新鮮味があり面白かった。psk/qamの信号判定や最適ダイバーシチ受信もこの方面からのアプローチで求まることに驚いた。写像関数としての通信システムの理解と最適退化写像について、今後は理解を進めていきたい。情報理論の基礎となる本であり、後進に向けてこのような素晴らしい本を著していただいたことに感謝したい。2024/02/25
U-tan
3
シャノンの the mathematical theory of communication に比べるといろいろかいてあるのだが,ひたすらわかったきにさせられる.同著者の『情報幾何学の新展開』を読む前にぱらぱら眺めた.物理と情報の境界に興味があるので,物理系と情報系の架け橋を考えるのに統計物理と情報幾何・情報統計力学の間にアナロジーだけでなく自然な測定・制御,変換の数理的な構造を見出したい.この本の出版後,Maxwell's demon,情報幾何,量子計算機・量子測定制御・量子通信などで進歩している.2014/11/06
Haruki
2
情報幾何学の先駆者でもあり多岐にわたって理論構築に貢献している著者の1970年の初学者向けの解説書。情報のエントロピー、通話路の容量を定義し、雑音下での容量最大化のための符号化の考え方(シャノンの定理)を紹介。大数の法則による指数的な収束性を雑音との区別に利用する。誤り訂正符号、標本化定理、不確定性関係と信号空間次元、情報幾何学も紹介。信号と雑音の距離を計量によって特徴づけ、雑音の性質を見たり、通信路の写像の性質を見たりするのに体系的になり見通しが良くなる。AMとFMの変調の特徴の信号空間的理解もできる。2022/11/20
ミュー
2
定義や定理の気持ちの部分が例とともに丁寧に書いてあって良かった。だからと言って議論や証明がいい加減かというとそうでもなく、過剰な形式化や厳密化をせず大事な部分だけが書いてありわかりやすい。この分野の一冊目として良い本だと思った。2019/11/02
-
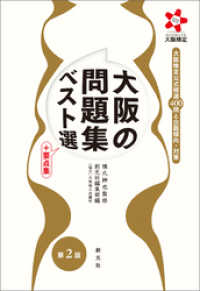
- 電子書籍
- 大阪の問題集ベスト選 +要点集 第2版…








