内容説明
若年のある時、在俗の名門武士が不明の動機で出家遁世した。真言浄土の思想に動かされながら、同時代の捨て聖たちとは対照的な生きざまを辿り、詩歌を通じてしか、いっさいの思想を語らなかった――西行とは何ものであったか。豊潤な感性を強靱な論理で見事に展開する西行論。「僧形論」「武門論」「歌人論」の3部構成で西行の〈実像〉に鋭く迫る!
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
かふ
22
西行は仏道としては、源信(恵心僧都)『往生要集』から法然・親鸞の浄土真宗の間にいた僧だという。源信は横川の僧都と言われ『源氏物語』でも影響を与えた僧で極楽・地獄世界を表した人である。つまり密教的な天台宗の流れから、法然・親鸞という誰でも御経を唱えれば成仏できるという浄土の思想、それはまだ念仏という形ではなく和歌だった。 西行の仏道は修験僧体験などもあって本格的な高野山の僧侶として、弘法大師伝説のように庶民の間に広まっていった。西行の月の歌はそのような静的な無常観が多いという。2024/05/06
浅香山三郎
17
「僧形論」「武門論」「歌人論」の3部からなる。語られた西行、或いは西行自らが騙つてゐたかも知れない西行像を仔細に腑分けして、最後に「歌人論」で、「心」といふ言葉の用例分析等を中心に西行の心境を読み解かうとする。面白いが再読しないと。2019/12/18
rou
8
後続する説話に見られる神話性を西行から剥奪しテクスト「山家集」に焦点を当て論考しようとしている。が、テクストへの実証性にムラが見られる気がしないでもなく…。また和歌の様式に対する論考にも誤りがある箇所には不安も出た。さらに研究者からすればハイライトとなる辞世の歌を始めとする桜花への憧憬も、浄土思想に集約されると余韻なく論じるあたりが、なんだか一杯飲み屋でオヤジに論破された感がある。手垢を鼻で笑う、その小気味良さ。西行を神話から隔離した後の歌人論での西行の「劇化」についての論考が最も楽しめる。西行は覚めて夢2014/01/02
にしの
7
面白かった。第一章で論じられる日相観往生・即身仏を至高とする浄土宗〜浄土真宗教徒の過激性とそこに孕まれた欺瞞、そこからの一向宗への流れなど、仏教史についてもとても勉強になった。源信と法然・親鸞の狭間、浄土思想の過渡期のなかに生きていたのが西行なのだ。読み応えが凄く、西行の歌群は勿論、万葉集から新古今等まで自在に行き来して、万葉〜平安の古歌の精髄に迫っている。吉本隆明の見識の広さを思い知らされる。吉本自身の著作『母系論』に連なる流れも読解に読み取れて興味深い。「中世の宗教者たちは、決して現在私達が宗教を見て2025/01/03
yunomi
3
西行にしろ和歌にしろ、知識は皆無なのだけれど、凄く堂々とした文芸批評だと思った。現代の作家とは違って、経歴を調べたり、インタビューをしたりする事も不可能な、西行の思想を現代に生きる私達が知る為には、遥か昔に遺された作品を「読む」事しか術がない訳で、だからこそ余計な情報を遮断し、作家や作品と正面から向き合う著者の姿勢は実に爽快。2010/09/14
-
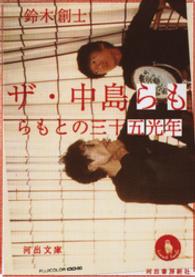
- 電子書籍
- ザ・中島らも 河出文庫








