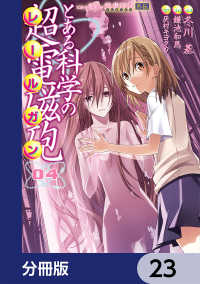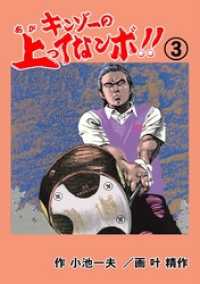内容説明
人間存在の危うさと脆さを衝く小説「マルクスの審判」、“国語との不逞極まる血戦”が生んだ新感覚派小説の「頭ならびに腹」とそれらを支える文芸評論「新感覚論」、1幕もの戯曲「幸福を計る機械」および「愛の挨拶」、新心理主義小説「機械」と、その後の評論「純粋小説論」等。昭和の文学の常に最前衛として時代に斬り込み時代と格闘した作家の初期・中期短篇、戯曲、評論を1冊に集成。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ころこ
47
古典でも新たな発見があるのは読まれるが、小さな問題を錯覚して深刻にしている様子なのを読むと、古色蒼然なのは否めない。『機械』以外を読んだことが無いため、全貌が分からないが、前半はそんなのばっかりでがっかりした。『純粋小説論』純文学と大衆文学を統合しようという意気や良し。しかし、それは誰もが考えていることであり、今でも試みられている。四人称とは勢いで五次元、六次元と言うのと一緒で、超越性を言いたいのだろうが具体性が無い。純文学が言文一致と哲学の不在を埋め合わせる役割を担っていて、文芸批評が補完している歴史的2025/06/23
メタボン
27
☆☆☆★ 新感覚論、純粋小説論は観念的過ぎて、難解で腹落ちしなかった。難しい言葉をこねくりまわしているだけで説得力がなく、むしろ腹立ちさえ感じた。愛の挨拶、幸福を計る機械といった戯曲や独白体の書翰は会話の軽さが上滑りしてこちらも今一つ面白くなかった。逆に実験的な短篇、コミュニケーションの稚拙さが悲劇を呼ぶ「機械」歌がシュールに響く「頭ならびに腹」踏切番の無罪「マルクスの審判」執拗なる三角関係「鳥」学者から筮竹を教わると同時にその娘に惹かれていく「馬車」は、文体の冴え、確かな方法論により、俄然面白く読んだ。2019/01/13
ハチアカデミー
17
いまなお新しい、純粋小説の試みの数々。互いの利害関係が絡み合いもつれていく様と、何かに操られるかの様な心理を堪能できる名作「機械」をはじめ、説明しつくせない愛について論じ合う男女の戯曲「愛の挨拶」、刊行された長編について書いた手紙という体の「書翰」もメタ・フィクショナルで面白い。「夢殿村」と呼ばれる病人達だけの村を訪ねる「馬車」は知られざる名作であった。作家案内にて筒井康隆、安部公房、大江健三郎の父であるとの一文があるが、日本現代文学の始点であると言えるだけの技巧と試みが詰まった一冊。技巧の源泉も知りたし2013/04/23
猫丸
15
短編小説8篇と評論2篇。小説とは人間精神運動の実験室であり、作者はそれを差配する研究者であれ、というモットーに貫かれた冒険的作品群である。横光の履歴からはロリータコンプレックスを抱えた躁鬱質の男が浮かび上がってくる。彼の内省は、あくまで理智に導かれながらも偶然要因の意味に方向を変えられる。ある意味で変幻自在、融通無碍。とても新しい。「小説構造の最困難な中で、一番作者に役立つものは、…(中略)…スタイルという音符ばかりのものである」(p.269「純粋小説論」)。筒井康隆がこれをそのまま受け継ぐ。2020/12/26
mstr_kk
11
再読。「純粋小説論」の有名な「四人称」の話は、「人称」の話ではないことがわかりました。純文学の思想性と大衆小説の面白さを兼ね備えた、ドストエフスキーのようなすばらしい小説、というのが「純粋小説」です。そして、そのためには一人称の「深さ」と三人称の「広さ」が同時に必要だよね、というのが「四人称」です。これを文字どおり「人称」の話だと思って読んでしまうと、まったく理解できないでしょう。その陥穽に、たとえば『小説技術論』の渡部直己さんがハマっているわけですが。これは「人称」の理論や技術論ではなく、エッセイです。2016/04/23