内容説明
第二次大戦中、日本の軍部は戦時体制の中で女性をどのように位置づけていたのだろうか。またその役割へと女性たちを動員するために、国家・メディアはどのようなプロパガンダを展開したか。本書は、戦時下において160万部の発行部数を誇った「主婦之友」をはじめとする婦人雑誌の表紙や口絵の絵画作品を徹底的に検証し、「戦時文化」のイメージが女性をどのように戦争へ誘導していったかを解き明かす。もの言わぬ「母」たちの体験した大戦はどのようなものであったのか、新たな戦争史の誕生。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
がらくたどん
64
女性を徴兵対象にしなかった日本で戦時下に婦人雑誌や啓発ポスター等で粛々と行われた「ある特定の女性像」への誘導大作戦の検証。視覚的にターゲットである女性の心情に直接訴える手法を丁寧に炙り出す。言葉での誘導よりも意識下に響くため、積極的に受け入れるほど達成感と高揚感が得られ違和感を持てばそれは概ね罪悪感へと変わる良くできた誘導方法。誘導の先にあるのは①戦闘員の増産②戦時雇用調整への寄与③戦争継続のチア行為。若桑の分析を経由して再度資料を見るとなるほどと感心する。まず異性愛カップルから出発し生まれた子どもには⇒2023/05/05
樋口佳之
27
男性中心主義は母性像崇拝を最大限に利用してきた。それが人間性の核心にふれ万人を感動させることを、この上もなくよく承知しながら。/止むを得ず協力させられた、といった程度のものではない。町内会、部落会、常会、隣組などのごくミニマムな部分においても、多少とも指導的な立場にいる女性たちは、かっぽう着にモンペをはいて、活気にあふれて活動していた。戦争はゲームであり、彼女らの熱狂はまさしくチアリーダーとしての熱狂/怜悧な、怜悧に傾きの感ありの記述に時代性も感じますが、今でも十分考えるべき内容でした。2017/12/18
しゅん
9
年表順に戦中当時の絵に対して具体的なコメントと解釈を施していく流れに勢いを感じる。プロパガンダとしての効果と絵画としての力量を同時に断言的に論じていく感じ。世でマザコンが蔑視語として使われているのに以前から納得いってないのだが、国家がすぐに「母」のイメージを戦争の道具にしていく(女性の多くもそのイメージを内面化していく)史実を論証された今となっては、余計に個人個人が「母」をしっかり捉えるべきではないかという気がしている。巧みなプロパガンダは今見てもまったく嫌な気持ちにならなくてすごいなと感じた次第。2020/09/23
ののまる
7
母子像だ、まさに。戦争システムとは家庭における家父長制を国家規模に拡大したもの。そのなかにおいて、女性は兵士を量産する母であり、その母は「母」国となる。「母の日」が制定され、女性のすべてを国家がコントロールし、女性もメディアや芸術による戦争文化によって,自ら動員されていく。2024/04/04
puwapuwa
3
家父長制の下くだらないものと抑圧されてきた女性たちが、戦時にようやく女性の立場向上の時期が来たことを喜んだが、本質は政府が国民の戦意向上のために逆手に取っただけだった(超要約)というあたりを読んだら泣けてきた。敵対している国同士で同じことをしているのだから虚しい。今の日本も何かとキナ臭いけど、いつの間にか国に組織されていたということにならないようにしっかり意識をもたないといけないのだと思う。少々難しかったけど大事なことが書かれています。もう限られつつある戦争体験者の声は貴重だと改めて思いました。2015/01/02
-
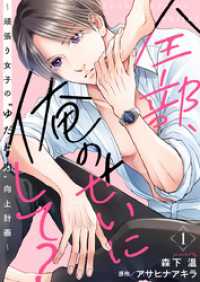
- 電子書籍
- 全部、俺のせいにして?~頑張り女子の”…
-

- 電子書籍
- ELDEN RING Become L…
-
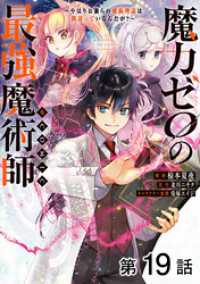
- 電子書籍
- 【単話版】魔力ゼロの最強魔術師~やはり…
-

- 電子書籍
- 神竜帝国のドラゴンテイマー【分冊版】(…
-

- 電子書籍
- ズバッと派遣!姫華(9) COMICエ…




