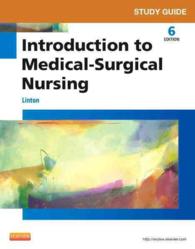内容説明
七一三年の官命によって編纂された「風土記」。全国各地の産物や土地、神話などを記す古代の貴重な資料である。その地誌としての性格をふまえ「風土記」を読み解けば、日本人に通底する心のありようが見えてくる。
【目次】
はじめに
第一章 「風土記」とはなにか
第二章 「風土記」の時間
序 説
第一節 「風土記」の時間認識 ―「古」「昔」「今」―
第二節 神の歴史 ―オオナムチ神話の国作り―
第三節 天皇の歴史 ―風土記巡行伝説―
第四節 祖先の歴史 ―「祖」「初祖」「遠祖」「始祖」「上祖」の世界―
第三章 「風土記」の空間
序 説
第一節 神話の空間認識
第二節 里長の役割と「里の伝承」
第三節 巡行伝承の空間的再配置
第四章 「風土記」からみた日本文化
序 説
第一節 松になった男女の「罪」と「恥」
第二節 天女の追放
終章 「風土記史観」でみた古代の日本
おわりに
引用文献および参考文献
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
bapaksejahtera
15
記紀と同じ頃の官撰文書だが、殆ど散逸し完本とされる出雲以外播磨肥前常陸豊後が一部残存、引用等の形で伝わる若干の各国風土記を参照しつつ一書に纏めた物。記紀の編年体記述に対し、風土記の特徴は今と昔を対置して、国の下位行政組織である郡と里(50戸程度の集団)の様を、特に地名由来等を中心に述べる、記紀とは異なる時間認識にある。スサノオが一貫して英雄的な出雲風土記、記紀と同じ神名乍ら、地域利益を強調した風土記登場の神々の機能記述が面白い。但し肝心の風土記から見る古代日本人の感覚記述は、例示が少なく不十分に留まった。2023/08/22
にしの
5
読。基本的知識がよくわかるが、日本人の心性の考察部分はうーん。罪と恥の関係。2024/12/17
彼方
1
風土記の名前は知っていても、実際の内容は知らなかった。 神話の時代から、今の日本人に通じる部分があることが分かった。 という、つまらない感想と同時に、続いて感じたこと。 だが、罪と恥のフレームワークの援用を排除する側のメンタリティにも適用すると話は別であろう。 こういう排除が罪と恥によって補強される状況こそ、今の日本のそこかしこで見ることができそう。 問題は神話の時代から根深くあるということですね。 それにしても、H市の図書館の旅行フェアで借りたのだが、旅行あんまり関係ないっす。2019/07/25
たま
1
興味深い。読み込みが足りなく、浅いけれど。2017/02/04
くらぴい
0
風土記の同類の本の中では読みやすさと、小説的に展開しない点に魅かれました。地元の近くの常陸国風土記というのがありますが、風土記の丘に子供時代行ったのを思い出しましたが、書物とは時代背景が違います。2017/06/28
-

- 電子書籍
- 美桜のペットさがしノート 大切な家族が…
-
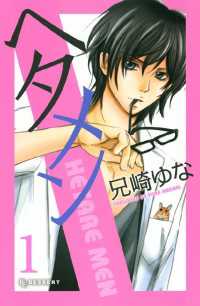
- 電子書籍
- ヘタメン1